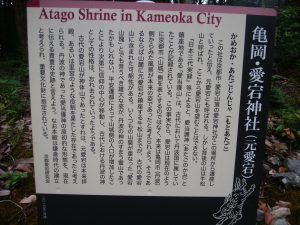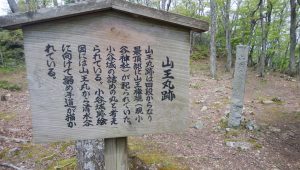今日も朝から快晴だけれど、次第に天気は崩れてくる予報。ツボ足なのでどこまで行けるかわからないけれど、大雪渓の上部あたりまでは行きたい。
朝5時過ぎに駐車場を出発して、まずは猿倉荘へ。

何となく以前の記憶ではこのあたりは雪が無かったように思っていたのだけれど、スキーで歩けるくらいの積雪量。
ここから林道合流までのちょっとした急斜面が朝の冷え込みでガチガチに凍っていて緊張した。思わず途中でピック付きストックのピックを出して、ピッケル代わりにして登った。
林道まで上がってからアイゼンを着用した。
本当はこれからずっと林道を辿らなければならないのだけれど、上からのトレースに惹かれて斜面をしばらく上がってしまった。実はこれは小日向山からのトレース。以前、白馬鑓ガ岳から滑った時はこの斜面を下りてきた。
何か変だなと思ったらやはり足元の先の方に林道を行く人たちが見えた。
元に戻るのは癪なので、傾斜の緩そうな斜面を選んで先の方で合流しようと思った。期待通り、長走沢のあたりで本来のルートに戻った。
振り返ると小日向山。

まだ気温が低いので雪面は凍結していてアイゼン歩きが快適だ。とは言っても日射しが強いので、羽織っていたジャケットを脱いだ。
歩き出して1時間半ほどで白馬尻のあたりまで来た。小屋は雪に埋もれてまったく見えず、テントが何張りかある。

しかし早くも雪が緩んできて、この先あたりから少し足が潜るようになった。
そして少し傾斜が急になったあたりで突然足元がずぼずぼと沈み込みだした。
どういう訳かそれまであったツボ足のトレースが消えている。それに下山者と少しすれ違ったのだけれど、彼らが下りてきたトレースが見あたらない。
トレースはスキーで上がったものばかりで、前方に見える人影もみんなスキーヤー。

少し上がればまた堅い雪面になるのではないかと期待したけれど、なかなかそうはなってくれない。
好天のせいで一気に雪が緩んできているので、このまま登り続けたら下りはさらに苦労することになりそうだ。前方のちょっとした傾斜を登れば大雪渓が拝めそうだけれど、そこまで行くのはかなり大変だ。
スキーで来ていれば何の問題も無く歩けるだろうけれど、こんな斜面は今となってはとてもまともには滑れない。
まだ登りだして2時間半くらいだけれど、いずれにしても大雪渓の途中で引き返すことになるので、そこまで頑張っても仕方無いと思えた。
まだ雪面が少しでも堅いうちに引き返した方がいいだろうと思った。そうと決めたら早々に下山に移った。
駐車場までは1時間で戻った。まだ8時半だけれど、これから天気が下り坂になるので、今日中に帰ることにした。
途中、五竜のあたりの車道に車を停めて、しばし山並みに見とれた。中央右のピークは白馬乗鞍岳だと思う。

まだ時間が早いので、このまますんなり帰ってしまうのはもったいないような気もしたけれど、山が近くに見えなくなってきたらもういいかなと思った。
途中で居眠り休憩を取りながら、午後4時には家に帰った。10時くらいには空を雲が覆ってきて、昼あたりからは雨もぱらついてきたので、山は思いのほか早く天候が崩れてきていたのではないだろうか。
新しい車は、信州までの往復850kmを無補給で走り切ることができた。高速がメインだったので、燃費は約19km/Lだった。期待の20km/Lには及ばなかったものの、燃料費は5千円少々で済んだ。1ヶ月前なら5千円を切っていただろう。
ディーゼル車は車両価格がガソリン車よりも高めなので、燃料費の安さで車両価格の値段差の元を取るのは難しいという意見もあるようだけれど、それにしてもこの安さはうれしい。これまで二十数年間ハイオク車に乗ってきた感覚からすると、とてつもなく安い。