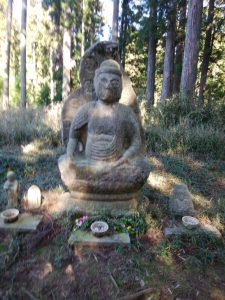先の日曜日(11/24)は高島トレイルを周回してきた。この日は少し前までの天気予報では雨予報だったのが、次第に雨が遅れてきたので、思い切って出かけることにした。
朝4時半に家を出て、途中でカップ麺とおにぎり、コーヒーで朝食をとって、7時前にビラデスト今津に到着した。ここに来るのは初めて。
初めてなので様子がわからず、立て看板で場所を確認してから平池(だいいけ)そばのスペースに車を停めた。実は離合用のスペースでした。

準備を整えて7時ちょっと過ぎに出発した。林道を少し戻って登山口へ。

道標に導かれて登山道に入る。

自然感たっぷりの気持ちのいい道。稜線に上がると木々の向こうに琵琶湖が望めた。

さらに進むと古道近江坂とバイパスの分岐に出会った。近江坂へ入る。
しばらく進むとバイパスと合流して、その後、林道と交差。

少し登ると大谷山からの高島トレイルに合流した。

このあとはしばらく素晴らしいブナ林が続く。思わず歓声が出る。

9時10分、最初のピークの大御影山(949.9m)に到着した。

ここでちょっと腰を下ろして一休みしようと思っていたのが、まさかの先客。単独行の男性でした。
写真を撮ったら早々に先に向かった。西側にはこのあと目指す三重嶽。

少し進んだところでぼたもち休憩にした。
一旦下って登り返して、小一時間で三重嶽分岐。

ここも気持ちのいいブナ林。稜線からは来し方の大御影山。

まさに極楽!!。こんなに気持ちのいい場所がこの世にあるのかと思えるほどの桃源郷だ。

11時ちょっと過ぎ、三重嶽(973.9m)に到着した。本日の最高峰。

幸い一人だったので、腰を下ろして琵琶湖や伊吹山、鈴鹿の山並みを眺めながらおにぎり休憩にした。真ん中左の突起が伊吹山。右の一番高いのが御池岳。その右に藤原岳。

さて、これから本日最後のピークの武奈ヶ嶽に向かう。比良の武奈ヶ岳には中学生以来もう何度も訪れているけれど、この武奈ヶ嶽はずいぶん以前から知ってはいるものの行くのは初めてだ。
結構距離があるので気持ちを引き締めて足を進めた。
テープマークを目印に進んでいたが、急坂を随分下ってきた。標高がどれくらいなのか確認しようと gps を眺めたところ、何とロストしていた!!。南の稜線を下っている。
テープマークはしっかりしているのでおそらくこのまま下って車道に出られるとは思うが、ここまで来て武奈ヶ嶽に行かずに終えるわけにはいかない。戻るしかないだろう。
標高差で100mくらいをヒイコラ登り返して間違った場所に戻ったら、標識の無くなった柱と高島トレイルのテープがあった。まったく気がつかなかった。

気を取り直して先に進む。若狭湾と琵琶湖が両方望める。これは若狭湾方面。たぶん小浜。

こんな稜線に結構大きな池がある。ここの水はどこから?

午後1時10分、ようやく武奈ヶ嶽(865m)に到着した。湖北武奈ヶ嶽と表されているが、どちらかと言うと湖西では?

今日、最後の展望で、比良山系。真ん中の一番高いのが比良の武奈ヶ岳。

高島トレイルに別れを告げて東側に下りる。

立派な道標があったのに、急に踏み跡が不明瞭になった。少ないテープマークを拾いながら何とか赤岩山(740.1m)まで来た。あとはひたすら下るだけ。

何の疑いも無くこの角川区という標識に従って下った。急坂を下ると下からバイクのエンジン音が聞こえてきた。
どれくらい下ったかなと gps を見たら、何とまたまたロスト!!。東側に下らなければならないのに南に下っていた。
たぶん集落までは下れるだろうが、戻る場所からは大きく離れてしまう。登り返すしかない。
結局、赤岩山まで登り返したが、東側には道は見あたらない。ヤブに少し入ってみたら、古いテープが見つかった。
古いテープを探しながら慎重に下った。こんな所を適当に下ったらとんでもないことになる。これまで何度も痛い目に遭ってきた。
それにしてももはや踏み跡すらほとんど無く、目印は古いテープのみ。しかもそれも倒木で先が見えない。

荒れた急斜面に難渋して、さらにテープ探しにも神経をすり減らし、午後2時35分、ようやく林道に下り立った。よくこんなルートでテープマークを見失わずに下りてこられたと我ながら感心した。

もうすでに快適だった稜線歩きの感動は醒めてしまっていたが、まだこの先、スタート地点までの林道走りが残っている。距離ははっきりとは確認してきていないけれど、おそらく1時間くらいはかかるだろう。しかも gps を見たところ、スタート地点まで標高差で 200m くらい登らなければならない。
石田川ダムを背にしてスロージョグで進む。

思ったより遠い。1時間たってもまだまだ先がある。対岸に天狗岩。

後ろから走ってきた軽トラの男性が「大丈夫ですか?」と声をかけてくれた。車道になってから初めて出会った車で、出会った車は後にも先にもこの1台だけだった。
もちろんここまできてキセルするわけにはいかないので「少し先に車を置いているので大丈夫です」とお返事した。
車に戻ったのは午後4時ちょっと過ぎ。出発してからちょうど9時間だった。後から調べたら車道部分はほぼ10km、トータル約32kmでした。
車に戻った時はやれやれという気分だったが、やはり今日のコースは本当に素晴らしかった。高島トレイルは部分的にはこれまでに何度も歩いているけれど、これまでで最高の雰囲気だった。
高島トレイルは全般的にアプローチが非常に不便なので、おかげで歩く人が少なくて自然感がたっぷり残っている。登山者が多いのは大谷山から三国山の間くらいだろう。ここはマキノ高原からすんなり来られて、周回もやりやすい。
今日のコースはぜひ雪のシーズンに再訪してみたいと思った。