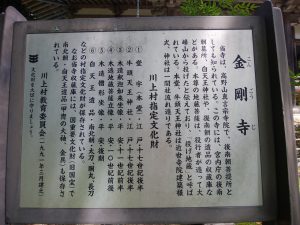6月に行った池木屋山のルートが非常に良かったので、また台高山脈へ行こうと考えていた。
テント泊の縦走は大変なので日帰りできる山ということで、白鬚岳の周回に行くことにした。
日曜日(8/4)の朝4時半に家を出て、奈良県川上村の神之谷(こうのたに)へ向かう。
いつものパターンで途中でカップ麺とおにぎり。そしてコンビニコーヒーで休憩を取って、google のナビに従って走っていたが、どうも様子がおかしい。入之波(しおのは)温泉まで来てしまっている。
登山地図を頼りにしばらく戻って、柏木から林道に入った。しかし登山口がよくわからない。
登山用の gps を起動させて現在位置を確認して、何とか登山口にたどり着いたが、駐車できるスペースはロープが張られて駐車禁止になっている。

仕方無く路肩にちょっとしたスペースのある場所に路駐した。他には車は無い。こんな所に停めておいて大丈夫だろうか・・・。

準備を整えて出発したのは7時40分だった。
登山道は駐車禁止のロープの林道を入って行く。

しばらく沢筋を行く。

きれいな滝。無名?

このあたりから道が険しくなってきた。滑りやすく、片側が切れた急斜面が続く。
最後の水場。

出発して1時間5分ほどで稜線に這い上がった。標高は 1000m を越えた。なかなか厳しい登りだった。下りでなくて良かった。

稜線に上がってからも道は険しい。次から次へとロープが出てくる。

9時9分に小白髭岳(1282m)を通過。

大峰はあまりはっきりは見えない。

白鬚岳がだいぶ近づいてきた。

急斜面は手を使って登る。

その時、ふと見たら目の前にマ、マムシ〜〜。手が届くくらいの距離。こちらをじっと見ている。
刺激しないようにしばしじっとしておいて、襲ってこなさそうな雰囲気になってからじりじりと離れる。
少し離れてから写真を撮ったけれど、残念ながらうまく撮れていなかった。
こんな所でマムシに噛まれたら生きて帰れる可能性は少ない。ポイズンリムーバーは持ってきているけれど、そんなくらいでは毒を吸いきれないだろう。
これまで登山者には一人も会っていないし、このあと誰かくるかどうかもわからない。おまけに携帯は圏外。
あやうくココヘリ(小型の電波発信機。ヘリ捜索用のため)のお世話になるところだった。
9時46分、出発して2時間5分で白鬚岳(1378.2m)に到着した。本日の最高峰。

ここでおにぎり休憩にして、周回コースへ向かう。下り始めはルートがわかりにくかった。

道というほどしっかりしたものは無く、たまにテープマークが出てくるくらい。ただし尾根スジはわりとはっきりしている。
白鬚岳への登りほどではないけれど、岩っぽいごつごつしたプチピークが続く。
白髭岳から50分ほどで 1168m ピーク。

しばらく下った所で写真を撮ろうと思った時に gps の画面が目に入った。何と、ロストしていた。あわてて戻ったら、間違ったのは 1168m ピークだった。
11時17分に切原(1131.9m)に到着した。ここで小豆モチ休憩。

切原を過ぎると道はこれまでよりははっきりしてきて、穏やかになってきた。1時前には下山できるかなと思いながら下って行った。
しばらく下ると林業のワイヤーが出てきた。もうすぐショウジ山。

11時53分、ショウジ山(984m)に到着。

このレール沿いに下りられるけれど、林道歩きはおもしろくないのでこのまま稜線を下る。
次第に下りが急斜面になってきた。今日はポールは持ってきていない。
所々にある赤テープを目印に下りてきたけれど、トレースが無くなって進む先がわからない。gps では本来のルートを少しはずれているようだ。
本来のルートに向かう方向に強引に行こうとしたけれど、倒木などでなかなかうまくトラバースできない。
斜面を見下ろしてみて、このまま一気に下ってしまおうと思った。
何とかずり落ちながら、下の方のブルーシートのある場所を目指して下った。

ブルーシートまで来たら道があるのではないかと期待して、確かにかすかな踏み跡はあったけれど、これもすぐに消えてしまった。
本来のルートからはさらに離れている。もうこのまま下るしかない。
地形図では沢沿いに道があるようなので、それに期待して下る。
何とか道の痕跡のような所まで下りてきた。

このままこの道が車道まで続いてくれることを祈りながら歩いた。土砂で崩れていやらしい箇所も何度かあった。
あと少しというところで堰堤が!!!。

万事休す。仕方無い。高巻きのためにまた斜面を這い上がる。
下の方は傾斜が急なので、傾斜が緩む所まで上がる。
しばらく上がったら、同じような人がいるのか、林業のためなのか、かすかな踏み跡が出てきた。これもあぶないトラバースが何度かあったけれど、ようやく本来のルートのテープに合流した。しかしここも道というほどはっきりしたものではなく、テープが無ければ見過ごしてしまいそうなかすかなものだった。
午後1時40分、ようやく林道に下り立った。ショウジ山から2時間近くかかってしまった。

ここから車を置いた場所までは5分足らずだった。今日一日、まったく誰一人出会うことが無かった。
こんなに追い込まれた気分になったのは本当に久しぶりだった。最悪、登り返せば何とかなるとは思っていたけれど、もうほとんど終わった気分でいた後にその選択はなかなか取れない。
恐いのは急斜面のトラバースで足元が崩れること。頭などを強打して気を失ったりしたら救助を求めることもできない。いずれにしてもこのあたりは携帯は圏外。何が何でも自力で下山しなければならない。
想定外のハプニングは多少であればいい思い出になったりするけれど、今日はそのレベルを超えていた。林道に出た時は胸をなで下ろした。
帰りは杉の湯の温泉でゆっくりして、6時前には家に帰ってきたけれど、どうもすっきりしない気分をぬぐえない。
やはりもっと早めに元に戻るべきだった。事故になっていても不思議ではなかった。運が良かったとしか言いようが無い日だった。