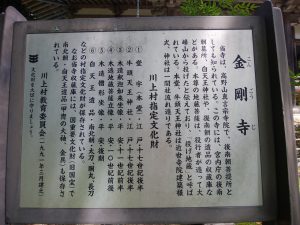そろそろ秋を感じたいので、岩湧山へ行こうと思った。
岩湧山だけではもったいないが、さてどういうルートにするか?
電車の駅をスタート・ゴールにしたい。岩湧山ならスタートは南海の紀見峠駅しか無い。問題はゴール地点をどこにするかということ。まさかピストンというわけにはいかない。
ルートとしてはダイトレを行って槇尾山というのが一般的だけれど、ここへ行くとバスに乗らなければならない。それに人が多そう。
和歌山線の駅は岩湧山からはかなり遠いので、残されたルートは北へ向かうしかない。
岩湧山の北にある一徳防山(いっとくぼうさん)は講座で行ったことがある。この時は逆コースで岩湧山まで足を延ばした。
講座の時はマイクロバスでの大名登山だったけれど、今日は平民登山。しかし北に下って車道を三日市町駅までなら走れそうだ。
ただ、これだけではちょっともの足らない感じ。なので、前菜で三石山(みついしやま)を味わうことにした。こんな機会でもなければ行くことが無さそう。
我ながらいいルート設定ができたとほくそえんで、難波から南海電車に乗り込んだ。途中、車内放送で、人身事故が発生してダイヤが乱れるとのこと。どこに転進するか考えていたら、事故が発生した駅はすでに通過した駅で、取りあえず紀見峠駅までは行けそうで一安心した。
9/16、午前8時17分に紀見峠駅を出発した。

今日は左に折れて三石山へ向かう。

しばらく車道を進むとショートカットできそうな山道が。

このあとも何度かショートカットして三石山を目指す。しかし歩く人が少ないようで、蜘蛛の巣だらけ。木の枝をぐるぐる回しながら歩いても、それでも蜘蛛の巣がしばしば顔に貼り付いてくる。
おそらくこれが三石山へ登る最後の山道。

なかなかの急登が続く。

9時28分、出発して1時間11分で三石山山頂(738.4m)に到着した。展望はまったく無し。

道標に従って岩湧山の方向に進む。しばらく下ったら荒れた林道に出た。
ツリフネソウ。

路面が荒れていてあまり走れない。

しばらくしたら舗装路に出た。走れる所は走っていたが、いつの間にかロスト!!

このまま進んでも岩湧山のそばの車道に繋がっていそうだけれど、おそらく遠回りになると思うので、戻って登山路を探した。さっきは死角になっていた。

登山路入り口の看板は「車両通行止」。荒れた登山路にバイクの轍があった。絶対に遭いたくない。石を投げてやりたくなる。
幸い、バイクに出会うことは無く、三石山から1時間少々でダイトレの稜線に出た。

しばし登ると快適なトレイルになる。これは走るしかないでしょう。

ただ、やはりここまで来るとハイカーがたくさんいる。
ついに出てきました。ダイトレ名物、木の階段。

岩湧寺への分岐。ここを下る予定。

岩湧山への最後の登り。

シラヤマギク(?)。

クルマユリ(コオニユリ?)。

11時7分、岩湧山(897.1m)に到着した。

展望場所から和泉葛城山(たぶん)。

ススキはまだこの程度でした。

山頂エリアは人が多いので岩湧寺への分岐に戻って、ここで今日初めて腰を下ろしておにぎり休憩にした。
そして20分ほどで岩湧寺の車道に下りてきた。

講座で来た時にどういう道を辿ったのかよく思い出せず、岩湧寺の方へ少し下ってみた。
シュウカイドウが満開。

やはり車道を上に上がるようで、ようやく一徳防山の道標に出会った。

岩湧山エリアを離れるとまた静かな山歩きが楽しめる。ただしまたもや蜘蛛の巣地獄。
編笠山(635m)。

もう少し涼しくて、蜘蛛の巣が無ければ最高なのだけれど。

下山は一徳防山手前の分岐を下る予定。

12時55分、一徳防山(541m)に到着した。そう言えばかすかな記憶がある。ぼたもち休憩。

分岐に戻る時、岩湧山の素晴らしい眺望に気付いた。

下山は尾根道で、途中から沢に下る道へ行こうと思っていたのだけれど、案の定、沢筋は荒れていて、分岐からわずかであっさり諦めて戻った。
尾根を下ると最後はゴルフ練習場のそばに出る。近づいてきたらそこらじゅうにゴルフボール。

つまりここまで飛んでくるということで、万全の注意を払いながら下った。
一徳防山から1時間足らずでゴルフ練習場まで下りてきた。あとは車道を三日市町駅まで走るだけ。

午後2時22分、三日市町駅にゴールした。

ちょうど駅のすぐ前にスーパーがあったので、ここのトイレで着替えて、ビールを買って一人打ち上げをやった。
ちょうどバルコニーから正面に岩湧山、右に一徳防山。

楽しい一日でした。