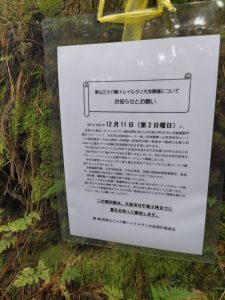10/24(月)の朝がやってきた。夜中に何台かの車が来ていて、朝にはすでに10台くらい停まっていた。平日の早朝だと言うのになかなかの繁盛ぶりだ。

天気は悪くないがとにかく風が強い。この季節でこの風だと雨具では心許ないので、まともなヤッケの上下を羽織った。
頭はフリース タイプの目出帽に簡易ヘルメットを入れた。手はブレスサーモのインナー手袋に防寒テムレスで完全装備で7時少し前に出発した。念のためにポールをザックにしのばせておく。

しばらく木の階段が続いた。

かなりの強風だったが何とか寒さには耐えられた。身体が温まってきたらちょうどいい感じ。
海側の展望がすばらしい。室蘭もよく見える。

30分少々で稜線に出た。

ちょうどここに先行者がおられて、「ブロッケン」が見えると教えて下さった。確かに噴火口側に小さな虹があって、ブロッケン現象ができていた。ただし薄かったので写真ではほとんどわからない。ブロッケン現象に出会うのは久しぶりだ。

強い横風を受けながら樽前山の東山(1021.9m)に7時37分に到着した。活火山のために本当の最高地点(1041m)には立ち入れない。風が強くて寒いので写真を撮ったらすぐに先に向かった。

少し下ると地形的な影響か次第に風が弱まってきた。荒々しい本峰が見えている。

このあたりでぐるっと見渡してみると、
しばらくなだらかな道を下り気味に進む。支笏湖がよく見える。

目の前に932m峰が座っている。登ろうとしている人が見えたが私はトラバースルートを行く。右に分かれるヒュッテ方面への分岐が2カ所あった。

このあたりまで来ると活火山の樽前山とはがらっと様相が変わって、樹林帯になってきた。

鞍部のあたりで下山予定の分岐をやり過ごしてしばらく進むと岩々した急な登りにさしかかった。なかなか厳しい登りで、ロープが張ってある場所も何カ所かある。

急登が終わってからも歩きにくい馬の背のような道が続く。
ようやくピークが見えたかと思ったが実はさらにまだ先だった。

ようやく本当の山頂が見えてきた。

9時21分、風不死(ふっぷし)岳の山頂(1102.3m)に到着した。誰もいなかったのでゆっくり自撮りした。

そうこうしていたら支笏湖側から単独行の男性が登ってきた。ちょうど入れ違いで下山開始。
来し方の樽前山を眺めながら進む。真ん中が本峰。左に東山。

駐車場にたくさん車が停まっていたわりには山ではほとんど人に遭わないと思っていたが、登ってくるパーティに二つほど出会った。
岩場を下りきってやれやれ一安心。
分岐からヒュッテ方面に下る。

少し下ったところでおにぎり休憩にした。樽前山の眺めもなかなかいい。暑いのでヤッケの上を脱いだ。下も脱ぎたかったがザックが小さくて入らないので致し方なくはいたまま。

支笏湖と1月に登った支笏紋別岳の山頂の電波塔がはっきり見える。下山後はぜひまた支笏湖へ立ち寄って、下から樽前山と風不死岳を眺めようと思った。

荒々しい沢筋。噴火した時に溶岩が流れたのだろう。

下の方では紅葉も美しかった。

11時11分に7合目ヒュッテに下山した。

平日だというのに駐車場は8割方埋まっていた。

後片付けをして支笏湖へ向かった。
ところがしばらくしたら本降りの雨になってきた。さらに支笏湖に着いたら1月には無料だった駐車場が有料になっている。山も見えないのに有料の駐車場に入る気にはならないので、立ち寄らずにニセコに向かうことにした。
雨は途中で止んだ。
ニセコに近づいて羊蹄山が目に入って愕然とした。

これほどの積雪は予想していなかった。アンヌプリ方面もかなりの雪だ。アイゼンは4本爪の軽アイゼンしか持ってきていないしワカンも無い。ピック付きストックのウィペットは持ってきているが。
とりあえずニセコ駅のすぐ前にある温泉に行った。これまでに何度か来ている。

先日のトイレ付き駐車場は観光バスがたくさん停まっていたので、道の駅に向かった。
明日は羊蹄山の予定だったのだが、この積雪にはちょっとびびった。2日ほど好天が続く予報なので、明日はチセヌプリあたりにでも行って積雪の様子を確認して、羊蹄山は明後日にしようと思った。天気予報でも明後日の方が寒気が緩むと言っている。
夜はぐっと冷え込んだ。念のためにというくらいの気持ちで持ってきたダウンシューズを履いて寝た。