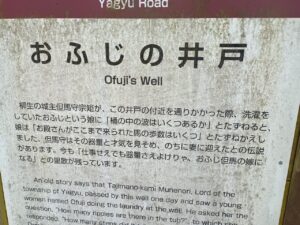11/12(日)は日曜日なので人の少なそうな山ということでニセイカウシュッペ山に向かうことにした。
ニセイカウシュッペ山は石狩川を挟んで黒岳の北側にある山で、今の私の体力でも何とかなりそうと思った。山名はアイヌ語で「峡谷の上にいるもの」という意味。
R273からはずれて狭い未舗装の林道を30分余り進んだところが登山口。駐車スペースはそこそこの大きさがあった。
1台停まっていて、準備をしているうちにあと1台やってきた。

8時前に出発した。

しばらくなだらかで穏やかな道を進む。
歩き出して1時間少々で目標の山が見えてきた。

そしてほどなく雪が出てきた。

しばらく進むと雪がしっかりついてきたのでチェーンスパイクを着用した。
ちょっとした岩場を越えるところが何ヶ所かあって、雪や氷が乗っていて、おまけに左側が急斜面なので慎重に越えた。
このあたりからはルートがほぼ見渡せる。

出発して2時間20分ほどで「あと1km」の標識。このあたりから逆に雪が少なくなってきた。
前に見えているのは前衛峰だが、これは左側をトラバースする。

あと少し。

11時ちょうど、ニセイカウシュッペ山の山頂(1878.9m)に到着した。

山頂には先行していた二人と、私を抜いていった三人がおられた。
天塩岳方面を望む。

三角点と山頂の標識があるが、実は真の最高地点(1883m)は少し東へ行ったところにある。

旭岳方面を望む。

写真を撮ったら早々に下山する。他の人たちはすでに下りていった。
岩場の通過は下りになるので行きよりも緊張した。
難所が終わって、雪が切れたところでようかん休憩にして、チェーンスパイクを脱いだ。
あとは淡々と下りるだけなのだが、小雨が降ってきた。
しばらくしたら雨が強くなってきたので雨具の上とザックカバーを着用した。
午後1時40分、登山口に下山した。雨は止んでいた。

下山中に、登ってくる二人パーティとすれ違った。日曜日にもかかわらず4パーティ、総勢8名の入山者だった。
温泉は「当麻ヘルシーシャトー」へ。JAF割り引きで630円。

ラジウム鉱泉ということで、長万部二股温泉ラジウム鉱石を使用している。本当の意味の温泉ではなさそう。
湯冷めしにくいやわらかなお湯とのことだが、効果のほどはよくわからない。
昨日と同じく、スーパー経由で道の駅に帰った。