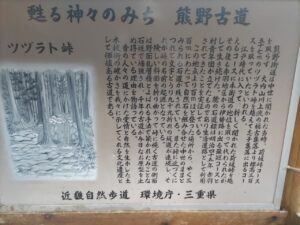4/24(木)は伊勢路峠歩き二日目でまずは馬越(まごせ)峠に向かう。
7時半にホテルをチェックアウトして、すぐに細い道に入った。何か違うような気がして一旦大きな道に出て、道路標識に従って馬越峠に向かう。

さらに標識に従って進むが、これは車道で、旧道ではない。どうも最初に入った道が正しかったようだが、今さら戻る気にもならないし、このまま進めばほどなく旧道に出会うはず。

こんなところなのに結構な台数の車に出会ってから無事旧道に合流した。

出発して30分ほどで馬越公園へ。

石畳が続く。

8時半に馬越峠に到着した。

東屋やベンチがあって整備されている。

一息ついたら天狗倉山(てんぐらさん)に向かう。
なかなか厳しい登りが続く。

あと少し。

峠から30分足らずで天狗倉山に到着した。
山の上は巨大な岩が二つあって、その間には役行者の祠が祀ってある。
まずは大きな方へ。このハシゴはなかなかビビる。

こちらの岩の上が山頂。

山頂からの眺め。尾鷲の市街地。

反対側の岩は木のハシゴ。

こちらの上からの眺めも尾鷲市街地。

役行者は扉の中。


さて、これからは尾鷲トレイルで東に向かう。
あまり標高が下がらずに馬越山(520m)。

ちょっと下ってカンカケ山(494.1m)。 ここは三角点がある。

天狗倉山から40分ほどかかってようやく「おちょぼ岩」に到着した。


展望は無し。

ようやく下りになったが、雨に濡れた落ち葉がたまった急な下りで、滑りやすくて緊張する。随所にロープもあった。
水地越峠。南北をつなぐ旧道が通っているもよう。

このあと少し登り返しなどがあって、10分ほどで小山浦狼煙場跡。ここで今日初めて腰掛けておにぎり休憩にした。10時12分。
ザックの横のポケットに入れていた小さなマットをいつの間にか紛失していた。おそらく滑って尻餅をついた時に衝撃で飛び出したのだと思う。お気に入りのマットだったので残念。

このそばに建っていた道標に「林道終点 380m」という表記があったが、林道までそんなに近いの? 海のそばまではまだまだあるはずだが。

急な下りはまだまだ続き、狼煙場跡から50分ほどかかってようやく林道に下り立った。

狼煙場跡にあった道標の写真を拡大してよく見ると、「林道終点 380m」の表記の横に小さな矢印が別方向に向いて書かれているのが見える。北側に向かう方向で、こちらの林道のことなのではないか。標識の板が指している方向と表記の方向が違うとは何たること!!
この道は明治21年に大八車が通れるように造られた「猪ノ鼻水平道」という道で、紀北町小山浦と天満浦の渡鹿(とうか)をつないでいる。
こんな橋が何箇所かあったが、とても大八車が通れそうにない箇所もあった。

ベンチのあったところであんパン休憩にした。
少し広い道に出た。渡鹿というのはこのあたりらしい。ここが尾鷲トレイルの起点。

少し行くと舗装された車道に出た。
甘夏がたくさん成っている。尾鷲は甘夏の栽培がさかんらしい。昨夜行った居酒屋で甘夏のジュースを少しだけいただいた。

車道を延々と歩いて、午後1時頃にようやく港のそばまできた。

このあたりは南海トラフ地震の津波警戒地域なので、こういう表記が随所に設置されている。

1時半くらいに尾鷲駅にゴールしたが、次の電車まではまだ2時間以上ある。
またイオンへ行ってロング缶のビールを買って、店の前のベンチに座って一人打ち上げをした。
その後、そばのコンビニでコーヒーを買って、それを持って駅に向かった。
列車で熊野市へ向かう。

車窓から今日歩いた山並みを眺めることができた。

電柱の向こうあたりが馬越峠で、左の山が今日は行っていない便石(びんし)山。右が天狗倉山で、なだらかな稜線の右端の突起がおちょぼ岩。そこからぐっと下る。
4時半頃に熊野市駅に到着した。

今宵の宿は駅から数分程度で、すぐにわかった。

ホテルの大風呂(と言っても入れるのは数人程度だが)でゆっくり、さっぱりしてから今夜も居酒屋へ。

昨日と同じく大満足でした。