先月は週末に用事が続いて、UTMF の2ヶ月前という時期なのに月間走行距離が 300km にも満たずに終わってしまった。唯一の成果は水晶岳だが、それもほぼ1ヶ月前のこと。
UTMF がほぼ3週間後ということを考えると、長い距離や時間をかける練習ができるのはこの週末が最後になる。しかし日曜日は雨模様なので、土曜日がラストチャンスだった。
できればロードでの長い距離の練習をやっておきたかったが、いくら猛暑は過ぎたとは言えまだまだ暑い。
と言うことで、先日トライして嵐山で終わってしまった京都一周トレイル全コースを、上桂まできっちりと仕上げることにした。
前回と同様に始発で出かけて、伏見稲荷を6時前にスタートした。

この時間帯はまだ涼しかった。四ツ辻からの眺めも快適。

住宅街を過ぎてようやく山道に入る。
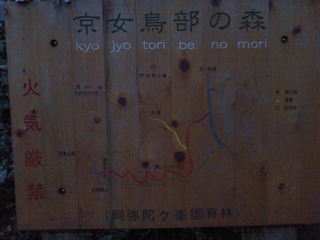
このところ雨が続いているためか、路面は結構濡れている。
7時前に清水山を通過。

インクラインは7時25分で、悪くないペースだ。

日向大神宮からの道は、このところいつも雨の岩戸のあるコースを行っているので、久しぶりに以前の本道の方へ行ってみることにした。ところがこの道、滑りやすい急なアップダウンで、こちらを行く人は少ないのではないかと感じた。
大文字山に向かっていると、前からランナーが。何と陸上クラブの仲間ではないか。職場に向かっているとか。
彼は 100km ウルトラは7時間少々。鯖街道ウルトラマラソンは何度も優勝している実力者なので、これくらい朝飯前なのだろう。
気楽に走っていたら、何とロスト!!。ちょっと変だなと思ったら、gps のルートからどんどんはずれてきた。このあたり、最近林道が延びてきていたりして、おまけに分かれも随所にあるので、注意していないと思わぬ道迷いになってしまう。
大文字山は8時17分くらいだった。腰を下ろしてジェルを補給する。

いつも通り朝鮮学校の校庭を横切って、バプテスト病院脇から山道に入る。
この先はいつも沢沿いの道を行っているのだが、今日は久しぶりに瓜生山を経由してみることにした。しかしトレイルルートの分かれより早く尾根道に入ってしまったようで、いかにも人があまり歩いていない感じ。蜘蛛の巣もたくさん残っている。しかし上に行けば瓜生山に向かうはずなので、そのまま進む。
少ししたら右側を少し下った場所に道標が見えて、そこがトレイルルートだった。
9時11分に瓜生山に到着。

このあたりからしばらくは快適に走れる場所なのだが、どうも調子が上がらない。何となくエネルギー切れのような感じがしたので、早めに対処しておこうと思って少し脇道に入って総菜パンを半分食べた。
帰ってからトラックデータを過去の記録と較べてみると、このあたりから徐々にペースが落ちてきていた。
雲母坂に出会う手前の沢で水を補給する。
雲母坂に入った展望場所は今日は素通りしようと思っていたのだが、ちょうどすぐ後ろにトレランのグループが来ていたので、すぐ後ろにつけられるのはイヤなので彼らを先行させるために展望場所で写真を撮った。

このグループはそれほど速くないので、私とあまりペースが変わらない。おかげでこのあとしばらくこのグループの後をぴったりと追いかけるような位置になってしまった。
私は山でもロードでも、練習会を除けば極力一人でマイペースで行きたい方なので、こういうのは精神的に疲れる。その影響かどうかわからないが、比叡山山頂エリアに出る直前で彼らと別れてから急に疲れが出てきて、明らかなガス欠症状になってきた。
スキー場跡の芝生に腰を下ろして、しばらく休憩することにした。空腹感があったので本当は固形物を食べたかったのだが、こういう状態になった時にジェルの補給だけでどの程度の効果があるのかを試してみようと思って、あえてジェルだけの補給にしてみた。
しばし目をつぶったりして、10分少々休んで再スタートした。何とまた、あのトレラングループに出会ってしまって、また気分が落ちた。
彼らは私より後から出発して追いついてきているので、私より速いペースで進んでいるのだが、何故かしばしば前方に現れる。
横高山の登りではまた追いついてしまった。

水井山でまた追いついてしまったので、私はここでおにぎり休憩にした。

しかしこのあたりでは前回よりペースが落ちていることがはっきりしてきて、完走に不安を感じるようになってきた。一時期よりは涼しくなったとは言え、やはりこういう持久的な運動をやるにはまだまだ暑い。
静原の自動販売機でいつも通りコーラを買ったが、近くのベンチに腰を下ろしてゆっくり飲んだ。
鞍馬には1時半くらには着きたかったのだが、もうすでに2時を過ぎていた。

ただ、この時はまだ気持ちは前を向いていて、自動販売機でポカリのボトルを買って、ザックのポケットの水と入れ直した。
ここからしばらく車道になるのだが、ここは前回とはまったく違ってまともに走れず、スロージョグでおまけに時々は歩きになるくらいだった。すぐそばを電車が通るので、思わず誘惑にかられそうになる。
二ノ瀬の小さな橋は、今回は通行できるようになっていた。

夜泣き峠への登りの手前で、階段に腰を下ろして総菜パン休憩にした。
冷静に考えると、今回はもはや時間切れだ。このまま進むとどう考えても上桂は9時は過ぎる。夜間走になるのは覚悟してきているのでヘッドランプは用意しているが、そこまで気持ちを持たせる自信が無くなってきた。
最大の問題は、途中でリタイアできる適当な場所が無いということ。
そんなことを考えていたら、何とまたあのトレラングループがやってきた。ずっと前に進んでいると思っていたのに。
随分迷ったが、今回はここで終了することにした。
前回に嵐山までは行っているので、今回はアクシデントが無ければ完走できると思っていたが、逆に変な余裕があって緊張感を持って臨むことができなかった。何だかんだ言っても 70km ほどあるコースなので、そんなに簡単に完走できるものではないのだが、それにふさわしい心構えができなかったのだ。
UTMF のおかげで京都一周トレイル全コースや比良縦走、水晶岳などにチャレンジしてきたが、おかげで自分にとって一番楽しいのは決められたコースを行くことではなくて、自分で目標を決めて地図を眺めながらコースを選択して、それを実行することなのだということがはっきりとわかって、レースやわかりきったコースを辿ることに対する興味がかなり薄れてきてしまったのだ。
何か UTMF が完走できなった場合の予防線を張っているようなのが自分でもイヤなのだが、これが今の偽らざる本音だ。
このコースに再挑戦することはもう無いだろう。京都一周トレイルコースを自分の意志で行くことももう無いだろうと思う。
武奈ヶ岳
日曜日は武奈ヶ岳。天気予報から考えると山ではほぼ終日雨という感じで、家を出る時も本降りだった。
しかし集合場所の坊村へ着いた時は雨はやんでいて、その後も時折小雨がぱらつく程度で、雨具は着用せずに歩き出した。
このコースは何十年も前に歩いたことがあるが、南西稜が気持ち良かったこと以外はまったく記憶が無い。
明王院から登山道に入る。

なかなかの急登が続くが、みなさん快調に足が進む。参加者の方でも前日と連チャンの方が何人かおられる。

樹林帯を黙々と登って、2時間半ほどで御殿山に到着。しかし残念ながら展望は無し。

先が長いので昼食はこの先のワサビ峠でとった。

樹林帯を抜けて南西稜にさしかかる。武奈のピークはガスがかかって見えない。

午前中の登りがこたえたのか、このあたりから遅れる方がチラホラと出てきた。
武奈ヶ岳(1214m)に到着したのは1時半に近かった。

天気が良ければここは人が多いのだが、今日は我々だけ。

小雨がぱらついていて、風が強いが、下山路に入るとすぐに風の当たらないルートになるので、私は上着は着ずに下山に向かう。
ここから八雲ガ原へは7月に縦走した時に通った。あの時に崩れていた箇所はそのままだったが、今回はあの時よりは安全なラインで通過した。
イブルキのコバに無事到着。

スキー場跡を通って八雲ガ原へ。

かつてはこのあたりにはロッジがあり、下からはゴンドラとリフトで上がることができたが、そういう施設はすべて撤去されている。ただ、それ以前のような自然に戻るのはなかなか難しそうだ。

少し登り返して北比良峠へ。

ここからはダケ道を下るが、そろそろ脚力が売り切れになった方がチラホラと現れる。イン谷からの数少ないバスの時刻に間に合うかどうかギリギリだ。
大山口には4時35分に到着した。

バスは4時40分なので、もう間に合わない。後は緩い下りの道を淡々と1時間ほど歩いて、比良駅にたどり着いた。
100%雨を覚悟していたのだが、結果的には時折小雨がぱらついた程度で、雨具は一度も着ることなく終了した。
日曜日の講座は一応初心者向けということになっているのだが、この日はなかなかのロングコースだった。gps では歩行距離は 15km くらいで、標高 1214m の武奈ヶ岳に登ったことを考えると、いささかハードな一日だったかも知れない。
ただ、前日との連チャンの方も含めてほとんどの方々は、疲労感はあるもののまだ大丈夫という感じで、なかなかのものだと感じた。
吉祥寺谷
先週末は土日連チャンで登山教室の随行だった。
土曜日は湖南アルプスの吉祥寺谷。堂山の北側にある谷で、元々沢登りはあまりやらない私は、こんな場所にこんな沢があるなんてまったく知らなかった。
軽い気持ちで出かけたが、実はそれなりの手応えのある沢だった。
石山からバスで新免まで行く。今年の春先に行った笹間ガ岳や堂山が望める。

今日のために新調したスパイクシューズに履き替えて、入谷する。

20数年前に比良の西側の沢を何本か遡行したことがあるが、おそらくそれ以来の沢歩きだ。
その当時は地下足袋にワラジで、フェルトシューズがチラホラと出てきていた頃だった。
沢歩きは次いつやるかわからないので、まともな沢シューズを新調するのはもったいないので、ネットの安い釣り道具店でフェルトスパイクシューズを探した。
しかし具合が良さそうなのはどこも在庫切れで、いろいろと漁ってようやく入手したものの、届いて開封したら実はフェルトの無いただのスパイクシューズだった。
そんなわけで、ぬるぬるの岩などにはかなり不安があった。
ちょっとした滝もあったりして、それなりの緊張感を持って進む。

堰堤が何カ所かあって、大きな堰堤の右岸をへつって広い河原に出て、そこで昼食にする。

ここを越えると徐々におとなしくなって、気楽な沢歩きになる。

最後は明治時代に作られたという古い堰堤を越えて、林道に出た。
後は林道、そして天神川の車道を下って、アルプス登山口のバス停まで1時間余り歩いて終了となった。
スパイクシューズはフリクションがしっかり効く時とずるっと滑る時の両方があって、どういう時に効いてどういう時に滑るのかよくわからない。
このシューズでは比良の西面のような沢は絶対にムリだが、おそらく登山教室の随行ではこれ以上のレベルの沢へ行くことはないだろうと思う。
上高地
先週末は家族旅行で福地温泉に泊まって、久しぶりに上高地を訪れてきた。
上高地は何度も行っているとは言うものの、もはや20数年ぶり。自家用車で入れなくなってからは一気に足が遠のいた。
久しぶりの上高地は随分とリニューアルされているように感じた。
バスターミナル近くの店や建物もきれいになっているし、河童橋周辺の店もまるで繁華街のそれのようだった。
天気は良かったけれど残念ながら稜線には雲がかかっていて、穂高の稜線を望むことはできなかった。

これまで観光で来たことがなかったので、今回初めてウェストン碑を眺めた。
ちょうどそのあたりから梓川の対岸に八右衛門沢が見えて、かつてこの沢をつめて霞沢岳に登ったことを思い出した。
その頃は山へ行く時は最低でもテントで一泊するのが当たり前で、この時も当然のように一人でテントを担いで登って、徳本峠でテント泊して、翌日、新島々までチンタラと歩いた。
またそんなことをやる日が戻って来るのかどうか、今はわからない。
三嶽、小金ヶ嶽
登山教室で多紀連山の三嶽、小金ヶ嶽へ行ったのは今月7日のこと。もう10日以上経ってしまった。
丹波篠山の近くで、多紀アルプスとも呼ばれる山域だが、私自身はこのエリアはまったくの初めてだった。
貸し切りバスで登山口の火打岩まで運んでもらう。

連日の猛暑で、これくらいの標高では下界とほとんど変わらないくらい暑い。
しばらくしたら鳥居堂跡。

さらに進むと大岳寺跡。

たかだか 700m 少々のエリアだが、多紀アルプスと呼ばれるだけあって、登山道はそれなりの岩場が出てくる。
11時30分に三嶽山頂(793m)に到着。山頂付近に祠があるが、あまり祠らしくない。

360度の絶景。これは京都方面。

昼食を取ったら大たわへ向かう。ここは滑りやすい急斜面で、ちょっとした転倒アクシデントがあったが、大事には至らず。
林道と交差する大たわに到着して一安心。

ここから小金ヶ嶽へ向けて登り返すが、ここも岩場が随所に出てくる。
振り返ると三嶽がどっしりと。

ちょうど2時頃、小金ヶ嶽(725m)に到着。

下山は最初は急な部分もあったが、次第におだやかな稜線になって、福泉寺跡を経由して下って行く。


沢筋をしばらく下って、バスの待つ火打岩に到着した。
暑い一日だったが、全般的に樹林帯で、日射しもそれほど強くはなかったように思う。
多紀アルプスと言われるだけあって、部分的にはアルペンチックな箇所もあって、なかなか楽しめる山域だった。
湖南アルプスや須磨アルプスなど、近場でもちょっと楽しめるような場所は以外とあるものだと再認識した。
競技場練習会
今日は久しぶりの練習会で競技場に出かけた。練習会はほぼ1ヶ月ぶりだ。
水晶の疲れはまだ残っていて、とてもまともな練習ができるような体調ではないのだが、今日を外すとまたしばらく参加できなくなるので、重い脚を引きずって出かけた。
予定のメニューはインターバル 1000m X 5 だったが、そんなメニューはできるはずもなく、ベテランの方のジョグに引っ張ってもらった。
ただし漫然と周回を重ねるのではなく、フォームは意識しながら走った。大腰筋を意識すること。そしてこれは最近読んだ本で仕入れたことなのだが、蹴った足をきっちりとたたむこと。
スピードのあるランナーはだいたいみんな蹴った足のカカトがハムストリングの方にしっかりと引きつけられているが、ああいうイメージ。
トラックランナーほどに引きつける必要は無いけれど、トレイルを走る場合はある程度は引きつける動作を身につけておかないと、足元の障害物を引っかけて転倒する危険性が高くなる。特に私はよく躓くので、このテクニックは重要だと思う。
省エネ走法と言うとどうしてもすり足で足をあまり上げない走り方になるのだが、ロードのウルトラならまだしもトレイルではああいう走りは危ない。
10000m を約 55 分で走り終えた。多少の余裕はあったと言えばあったのだが、一人だったらこれだけは走れなかったと思う。午後は一段と身体が重かった。
トレランザック
水晶の疲れがまだ残っている。まだまだ身体が重い。おんたけウルトラの後よりはるかに疲れている。ただし筋肉痛はまったく無い。
水晶では今年購入した Ultimate Direction の PB Adventure Vest というザックを使用した。このところはロングルートの時はほとんどこれを使用している。
UTMF もこれで行こうと考えていたのだが、水晶で UTMF の時に近い装備を背負った結果、これでは UTMF では容量不足になるとわかった。
トレランザックは、一日行動できるくらいの容量のものは3つ持っている。
数年前、初めて買ったトレランザックは Gregory の Reactor。

容量は 11L くらいで、ちょっとした着替えを入れてもだいたい大丈夫だ。
しかしこのタイプ(この当時はどんなメーカーでも基本的には同じような作りだった)は小物以外はすべて背中に背負うことになるので、水分補給は手軽にやろうと思うとハイドレーションということになる。
私は最低限度スポーツドリンクと水、さらにできればお茶の3種類は持ちたいので、スポーツドリンクと水は500ml のペットボトルにハイドレチューブを使って、お茶は休憩時にザックを下ろして飲んでいた。
しかしこういうスタイルだと水分の残量がわからない。暑い季節だと 500ml なんてわりとすぐに無くなってしまうものだ。
おそらくそういう理由からだと思うが、トレランの世界でもボトルをザックの肩ベルトに装着しているスタイルをしばしば見かけるようになってきた。これならいつでも残量確認できるし、補給もザックを下ろさずに簡単にできる。
そこで、登山用品として売られている外付け用のボトルポーチを購入して Reactor に付けてみたが、走るとどうしてもボトルが揺れて身体に当たる。はやりこういうのは歩きの登山やハイキングでしか使えない。
仕方無く2年前に購入したのは Salomon の XA Skin Pro 10+3。

いわゆるベストタイプというモデルで、普段は 10L。容量調節用のジッパーをはずすと 13L になる。
やはり最初からボトルを前に入れるようになっているモデルは具合が良く、これ以降 Reactor はほとんど出番が無くなってしまった。
しかし使い続けていると不満は出てくるもので、これの欠点はサイドポケットにジッパーが無いというこ。ストレッチ素材で押しつけているだけなので、背負っている時に中のモノが飛び出すようなことはまず無いが、ザックを下ろした時にぽろっとこぼれてしまうことがある。
特に前にボトルを入れるタイプは下ろして置いた時にボトルの重さで変な位置になってしまうことが多く、背負った時に十分に注意しておかないと落とし物をしてしまう。
そういうこともあって、前面のボトルポーチは水分を入れるのは片方だけで、もう片方に携帯やジェルなどを入れて、サイドポケットはゴミ袋や手ぬぐいなど、万が一落としても致命的にならないものだけを入れるようにしてきた。
ただこうすると重量のバランスが悪くなり、ボトルを入れた方の肩が疲れるというようなことも経験した。
この春になって UTMF に出場できることが決まった時、装備をどうするかということを考えた。できるだけ慣れているものが良いが、欠点のあるものは対策を考えておかなければならない。
ザックに関してはやはりこの Salomon のモデルでは不安だと思った。UTMF のような、おそらく極限状態になるであろう時に、落とし物に注意するというようなことは不可能だ。
と言うことで、この春に新たに購入したのが Ultimate Direction の PB Adventure Vest。

容量は 11L ということでほぼ Salomon と同じだが、サイドポケットにはジッパーが付いており、ボトルポーチの上にも小さなポケットが左右に付いている。サイドポケットの身体側もマジックテープの付いたちょっとしたポケットになっている。ここはいつもゴミ袋入れにしている。
これはかなりの優れものだった。これだとボトルポーチは両方にボトルを入れられて、貴重品もジッパー付きのポケットに入れられる。
本体背面にはバンジーコードが付いているので、帽子などはここにはさんでおける(実は今回、ここにはさんでいたゴアテックスの帽子をいつの間にか無くしてしまっていた)。
これを購入してからは今度は Salomon の出番がほとんど無くなってしまった。
機能的にはまったく問題無いのだが、唯一の問題は私にとっては若干容量が小さいということ。実質的には Salomon よりも小さいと感じる。
本体はストレッチ素材なので多少は詰め込むこともできるが、トレランギアの宿命で、軽量化を重視しているために耐久性が犠牲になっており、角張ったものなどをムリに詰め込むと簡単に破れてしまいそうだ。
これまでの日帰りトレランではこれでも対応できているが、UTMF では補給食などをたくさん持つ必要があるので、これではとても入りきらない。それに冬場になって防寒具やアイゼンということになるとまったく不可能だ。
財政の余裕も無いのでどうしたものかとネットをサーフィンしていたところ、たまたま見つけたのが RaidLight の Ultra Olmo 12 というモデル。これの中古が 9,800 円で売っていた。

モデル名の通り 12L という容量なのだが、いろんなレビューを見てみるとかなりたくさん入るらしい。
ベストタイプでは無く、Reactor のようなトラディショナルなスタイルでボトルポーチが前面に配置されているという感じ。おかげでザックの下部が大きく、このあたりにかなり荷物を入れることができそうだ。おまけに外から突っ込めるポケットも大きなものが付いている。
ちょうど Yahoo カードを申し込んで 3,000 ポイントをもらっていたので、思い切ってこれを購入することにした。
昨日の午前中に発注したら、早くも今朝には到着した。
箱から出して見た瞬間、これなら容量は大丈夫だと確信した。カタログスペックでは PB Adventure より1L大きいだけだが、実際は 1.5 倍くらいは入りそうだ。
中古だが使用感はほとんど無い。
肩ベルトや背中の当たる面にわりとしっかりしたクッションの素材が使われており、疲れてきたらこういうのが以外と身体に優しくて助かるかも知れない。
小さなジッパーがたくさんあって、かなり凝った作りになっている。おそらく重量そのものはやや重めだと思う。
唯一の問題点はウエストベルトが長すぎて、一番縮めた状態でもきっちりとしたポジションにならないということだが、私の場合はザックのウエストベルトはこれまで購入したすべてのモデルでこういう状態だった。
ベストタイプはウエストベルトが無いが、Reactor でもこのような状態で使ってきたので、おそらく大きな問題にはならないだろう。
早く実際のフィールドで使ってみたいが、今月はすでにすべての週末に予定が入っており、ロングトレイルに行けるのは来月になってからだ。しかし来月末は UTMF なので、疲れの残るようなロングは避けなければならない。
涼しくなってくれたら近場でもいいのだけれど、残暑が厳しかったらまた遠くへ出かけなければならない。
そんなわけで、このところ登山地図をつらつらと眺めている。
水晶岳
水晶岳はどこからアプローチしても遠い。北アルプスの最奥部と言ってもいいくらいだ。一般的には2泊3日は必要だが、何とかここを1日で登頂できないかと思い描いていた。
一番可能性の高そうなのは新穂高から双六小屋、三俣山荘を経由するルート。他には折立から太郎平、雲ノ平経由。それと、七倉からブナ立尾根を上がって野口五郎経由くらいだろうか。
実は2年ほど前に七倉から一度チャレンジした。マウンテンバイクで高瀬ダムの上まで行って、真砂岳の手前あたりまで行ったのだが、終盤に疲労困憊してブナ立尾根を下るのが不安だったので、そこで断念して引き返した。
実は高瀬ダムの道路は東電の管理で、自転車の走行は禁止されているらしい。出発が深夜だったので気が付かなかったが、戻って来た時にゲートで呼び止められた。
雲ノ平経由は折立までが遠いので、今回、新穂高からの往復にチャレンジすることにした。双六までは1日で往復したことがあるので、前半のルートはだいたい様子がわかっているというのも安心材料だった。
連日の猛暑で、新穂高でもかなり暑い。車のエアコンをかけたいくらいだったが、そういう訳にもいかず、窓を少し開けてエアマットの上でしばらく横になった。
出発したのは午前1時前。満天の星空だ。仙丈の時と違って月がまだ出ていないので、星空が素晴らしい。仙丈の時と較べると気温も低めで、湿度も低い。おおむねこの時期のこのあたりの天候という感じ。
ウエアは上はノースリーブのアンダーの上に半袖のトレランシャツとアームカバー、下はヒザ下までのトレランタイツ。シューズは HOKA にした。
左俣林道をスロージョグで進む。笠新道の出会いを過ぎ、ワサビ平小屋を通過して、小池新道取り付きまで1時間少々だった。
小池新道に入るといきなり雪が現れてびっくりする。

※帰りに撮った写真
こんなところでこんな雪なら、上部はどれくらい雪が残っているのかと不安になった。今回はアイゼンは持ってきていない。
しかしこれから先は雪はまったく無く、かすかに記憶の残る石畳のような道をヘッドランプの明かりで登って行った。
こんな時間帯でも二人パーティ2組を抜いた。いずれも中年の夫婦という感じで、ちょっとびっくりした。
鏡平へ向かって東に折れる場所ではテントを張っている人がいた。昔はここから沢をつめて大ノマ乗越に上がる路があったようだが、今は残雪期以外は使われていないようだ。
鏡平山荘へは3時半過ぎに到着。すでに起きて体操をしている人がいるが、あたりはまだ真っ暗。しかし東の空に明るい三日月が出てきた。
このあたりまで来ると結構寒い。先週の仙丈とは大違いだ。
弓折の稜線に出たあたりでようやく東の空が白んできた。
双六小屋に向かってしばらく下る。戻って来た時はここをしっかり登れるだろうか。
双六小屋がようやく見えてきた。

双六小屋には5時頃に到着した。ジェルを補給する。止まっていると寒いので早々に出発。
双六に向かう斜面を登っている頃、後ろに素晴らしいご来光を眺めることができた。

数年前に双六を往復した時は新穂高から4時間半くらいで登っているので、おおむね同じくらいのペースだ。しかし今日はこれから先が長い。水晶まで7〜8時間で行ければと考えていた。
今回は双六へは行かずにトラバースルルートで三俣へ向かう。
彼方に目標の水晶が見える。真ん中の大きいのは鷲羽岳。まだまだ遠い。

太陽が上がってきて、西側には自分の影が。

三俣蓮華(2841m)はピークを踏んでおくことにした。なかなかの急登で、10 分くらいだったが結構なアルバイトになった。

槍穂高連峰がくっきり。

三俣山荘へは出発して6時間くらいで到着した。

鷲羽岳(2924m)への登りは厳しかったが、何とか1時間弱で8時前に到着。

ここからの下り、そしてワリモ岳への登りはさらに厳しかった。ワリモ岳山頂へは行く気にならず。

水晶から戻ってきた時にまたこのアップダウンを繰り返すのは到底たまらないと思って、帰りは西側の谷ルートへ行こうと思った。
疲労感はかなり大きいが、ここまで来たらもう行くしかない。9時前にようやく水晶小屋に着いて、パワーバーでエネルギー補給をした。

このあたりまで来ると登山者は少ないのではないかと思っていたが、そんなことはなかった。百名山人気なのだろうか。ただしツアー登山のような団体は見かけない。小さなデイパックの人が多く、三俣山荘に泊まって来られているのではないかと思う。
念願の水晶岳(2986m)の頂上へは9時45分に到着した。出発してほぼ9時間かかった。

360 度の絶景で、富士山もはっきり見える(この写真ではわからないが)。

懐かしの野口五郎岳。

復路は岩苔乗越から沢のルートで三俣山荘へ向かう。
ちょうどこのルートの最低標高のあたりが、黒部川の水源地ということになっているらしい。

三俣山荘まで戻ったら、後は往路と同じ路を戻るだけ。しかしちょっとした登りが何カ所かあって、気分は重い。おまけにこのあたりで gps のバッテリーが切れてしまった。
三俣山荘に戻ったのが 12 時過ぎくらいで、この頃から急激に気温が上がって蒸し暑くなってきた。森林限界を超えているので直射日光を浴びて暑いことこの上ないが、帽子をかぶる気にはなれない。
双六下のトラバースルートを歩いていたら、稜線の下のあたりに熊がいた。随分以前に鹿島槍の稜線直下で熊を見かけたことがあったが、結構高い所までやってくるのだ。

※赤いマルで囲んでいるところ。
所々現れる登り返しも何とか歩き続けている。もう出発してから 12 時間以上たっているので疲労はかなり蓄積しているが、こういう状態のまま長く歩き続けられるようになってきた。
双六小屋に戻ったのは2時 12 分くらい。水を口に入れながらでないとぼた餅がノドを通らない。
鏡平山荘へは3時 35 分くらいに戻った。残念ながら槍の頂上部は雲がかかっていた。

石のごろごろした路を転倒しないように注意しながら下って、5時過ぎにようやく左俣林道に出た。

林道は緩い下りで路面も悪くないのだが、さすがにもう走ることはできなかった。たまにちょっとジョグのリズムで進むのが精一杯。
駐車場に戻った時は6時を過ぎていた。往路9時間、復路8時間半、距離約 45km だった。
仙丈ヶ岳
先週末は随行で仙丈ヶ岳へ行ってきた。これ以上望めないような好天で、アルプスとは思えないほどの暑さだった。
仙丈ヶ岳は学生時代に一度行っただけで、何と 41 年ぶりだ。その時はまだ林道も開通していなかったので、戸台から戸台川の河原を延々と歩いたことだけが記憶に残っている。
土曜日は貸し切りバスで京都から林道入り口になる仙流荘まで行って、ここで林道を走る村営バスに乗り換えて北沢峠で下車。ここから数分歩いた北沢長衛小屋で宿泊する。
林道のバスは路線バスだが、我々はほぼ1台ちょうどくらいの人数なので、貸し切り状態ですぐに出てくれた。
バスの運転手は観光バスのガイドも兼ねているようなノリで、景色やら植生やらを詳しく解説してくれる。立山の室堂に向かうバスも録音でガイドを流しているが、はるかに親切で知識も豊富だ。
遠方に仙丈の望める場所が少しの間だけある。

戸台川の左岸上部を行くようになると、左側に鋸岳の稜線から甲斐駒の眺めが素晴らしい。鋸岳の鹿窓も見える。
植生も豊富で、アサギマダラもそこらじゅうに飛んでいる。
北沢峠へは午後2時半くらいに到着した。2000m を少し越えているのだが、涼しさはまったく感じられない。

峠のちょっとしたエリアで植物が保護されているのだが、名前は忘れた。

林道とトレイルを東に数分下って北沢長衛小屋に到着。

夕食まで1時間半ほど時間があったので、手ぶらで甲斐駒方面に向かってみた。ずっと樹林帯で、わずか1カ所戸台方向が少し望めただけで、30 分ほど登ったところで引き返すことにした。

夕食後は持参したワインを楽しんで、日曜日は朝の3時半にヘッドランプで出発する。
2000m あたりまで来るとこの時期でも早朝はひんやりするのだが、そういう寒さはまったく感じられない。
夜が明けて、樹林帯を抜けると、360 度の大展望が広がっていた。
北は甲斐駒とその向こうに八ガ岳。

西は北アルプス。

東は北岳、そして富士山。

地蔵のオベリスクもはっきり見える。

小仙丈(2854m)まで来ると上部が白くなった御岳が望める。

仙丈まではもう一息。

8時半頃、ようやく仙丈ヶ岳(3033m)に到着した。

日本の山の標高トップ3そろい踏み。

富士山の雲がちょっと異様で、箱根の噴煙ではないかと思われたのだが、そうではなかったようだ。
下山は北側を廻って仙丈小屋へ。

藪沢のカールがきれいに望める。

馬ノ背ヒュッテのあたりは鹿よけネットで高山植物を保護している所がたくさんある。
藪沢を渡るあたりには上部にナメ滝。

最後は北沢峠に直接出るルートを取って、12 時半くらいに無事全員下山となった。

標高差 1000m を一日で登下降するということで、脱落者が出るのではないかという懸念が少しはあったのだが、結果的には全員無事登頂することができた。
体力的に厳しかった方もいらっしゃったと思うが、結果的にはいい思い出になったのではないかと思う。
私自身も久しぶりの南アルプスで、山々の大きさを実感できて、楽しい山行だった。
貝ヶ平山、香酔山
昨日は登山教室の随行で奈良県の貝ヶ平山と香酔山へ行ってきた。酷暑が予想されたが、おおむね曇りで、最後の車道を除いてはずっと樹林帯の中だったので助かった。
※gps のトラックデータのせいで実際のトレースよりもギザギザになっています。
朝は近鉄の榛原駅からタクシーに分乗して鳥見山公園まで行く。なかなかの急登で、ここを歩くとかなりのアルバイトになるだろう。標高はすでに 600m 近い。

そばに小さな池があって、ぐるっと一周してみる。

歩き出したのは 10 時くらい。少し登ると見晴台があって、大台や台高方面が望めるが、雲がかかって遠方は見えない。音羽三山も上部は雲に覆われている。

30 分ほどで鳥見山(734m)を越えて、所々ロープの張ってある急登をあえいで 11 時半に貝ヶ平山(821m)に到着した。

昼食をとってから来た道を少し戻って、小さな道標に導かれて東にそれて香酔山へ向かう。

踏み跡程度の道をドンと下って、ガンと上がって、20 分ほどで香酔山(795m)へ到着。

このまま東に向かうと延々と車道を歩かなければならないので、先ほどの分かれに戻って、登ってきた道をさらに下る。
少し下って、テープ標識のみの分かれから玉立(とうだち)へ向かう。

少し下った場所では貝ヶ平山という名称の由来と言われる、貝の化石がたくさん取れる。みんなで化石採集に励む。

30 分ほど下ると玉立の棚田エリアに出た。
道ばたには大きなヤマユリ。

東の方に見えるのは鎧、兜か?

この下にバス停があったが、次のバスまで1時間ほどあったので、暑い車道を 30 分ほど歩いて榛原駅に到着した。
鳥見山公園のあたりは東海自然歩道が通っているので、随分以前に一度は来ているのだが、まったく記憶が無い(山には登っていないが)。
暑さは予想したほどひどくはなかったが、湿度が高かったので、歩いた距離や標高差の割には疲労感の大きいコースだった。
榛原駅そばのコンビニで 500ml の缶ビールを買って、電車の中で呑みながら帰ってきた。
