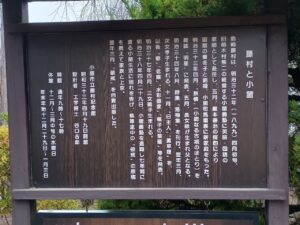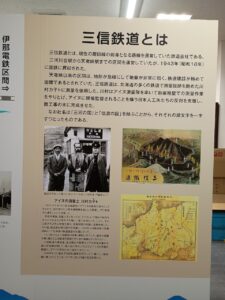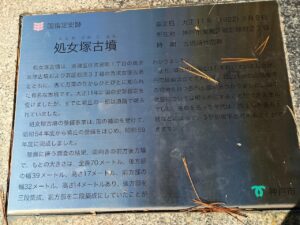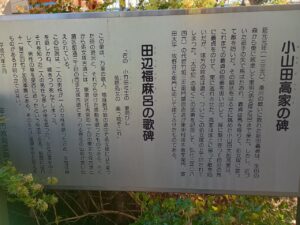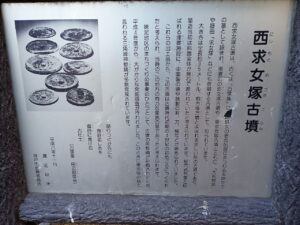先週の比叡山が思った以上に快適だったので、またどこかへ行きたくなった。
それなりの標高差があって、交通の便が良いところと言えばやはり愛宕山だろう。
ということで、2/12(木)は愛宕山に出かけることにした。
個人的に愛宕山へ出かける時はいつも保津峡駅からのルートで登っている。保津峡駅を午前10時に出発した。

橋を渡って登山口へ。

このルートは序盤に急登がある。今の心臓の状態でこの急登を上がり切れるかどうかいささか不安だったが、ポールを持って取りついた。
10分少々で何とか登りきって、なだらかなところまで来た。

昨日は久しぶりの本降りの雨だったのでところどころ地面に水溜りがあったりしたが、おおむね気持ちのいい道で、11時過ぎに荒神(こうしん)峠まで来た。


水尾へ行く道を左に見送って、稜線をガシガシ登る。
峠から40分ほどで表参道に合流した。

数分で水尾の分かれ。

少し行くと石段になる。いよいよ雪道になってきたので慎重に登って黒門へ。


出発から2時間以上かかって、ようやく神社のエリアまで来た。

本堂への階段は一部が除雪されている。

12時半過ぎに本堂に辿り着いた(924m)。

「火廼要慎」のお札を買って、石段の麓の東屋でおにぎり休憩にした。
下山は月輪寺の方へ。

35分ほどで月輪寺。

ここはいつもそばにシカがいる。

午後2時15分に林道に下りてきた。

林道を十数分歩いて一周トレイルのルートに合流した。

ここから10分足らずで表参道上り口の二の鳥居。

そのまま清滝川沿いの一周トレイルのルートを進んで、落合で腰を下ろしてカップケーキ休憩にした。

水尾への車道を歩いて、午後3時50分に保津峡駅に戻ってきた。

ちょうど4年前のこの時期にほぼ同じコースを歩いている。その時と比べるとやはり時間はかかっているが、おおむね加齢による体力、筋力の低下の影響という感じで、心臓の影響はあまり無かったように思う。
先週の比叡山もわりとしっかりと歩けたので、体調さえ悪くなければまだそこそこは歩けそうに思う。
このままの調子が続いてくれればいいのだが。