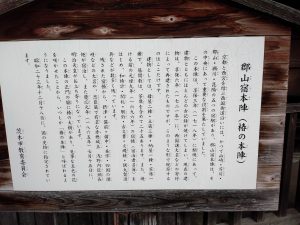4/17(日)は講座で品谷山と廃村八丁へ行ってきた。以前このあたりを個人的に歩いたのはもう6年前だった。
京阪の出町柳駅に集合して、広河原行きのバスに2時間近く揺られてようやく登山口の菅原に到着した。

トイレが一つしかなく、歩き始めたのは10時過ぎだった。
集落の奥から登山道に入る。前回来た時は沢筋をそのまま詰めてしまって苦労した。

少し登るとイワウチワの群生が出てきた。

50分ほどしっかり登ってダンノ峠に到着。

今日はここから品谷山に向かう。

25分ほどの登りで稜線に出た。

ちょっとだけ残雪。

タムシバ?

この先で他の団体パーティが昼食をとっていた。
我々はもう少し先に進んでちょっとしたスペースで昼食にした。

昼食後、15分ほどで品谷山(880.7m)に到着した。

このあと廃村八丁に向かうが、しばらく倒木などでずいぶん道が荒れていた。
品谷山から20分少々で峠に到着した。

廃村八丁へ向けて沢筋を下る。

20分ほどで廃村八丁に到着した。前回個人的に来た時はこの沢が飛び石で渡れなくて、あきらめてジャバジャバと渡った。

時間があるので神社の跡に行ってみる。少し西に向かってから参道を上がる。

すでに完全に崩壊している。

さて、菅原に向かって戻る。沢を何度も渡りながら進む。

途中から急斜面を這い上がって四郎五郎峠へ。

八丁平から移転した同志社の新心荘。自然環境研究室と書かれているが、あまり利用されているようには見えない。

菅原まで下りてくるとこのあたりではまだ桜が満開。

その後、午後5時半過ぎのバスで出町柳に戻った。