今日の随行は愛宕山北方の朝日峯だった。
今日ももちろん私は初めてで、山名を聞いたことも無かった山。
集合は高雄の奥の細野口というバス停。京都駅から1時間以上かかって 10 時前にようやく到着した。

愛宕山へ続く林道をゆっくり登って行く。
最近何度も見かけてさすがに覚えたタニウツギ。

今日、何度も見かけたエゴノキ。

これも一昨日に続いてコアジサイ。

しばらく行って、愛宕山へ向かう道から分かれて松尾峠へ向かう。愛宕山は右。

右の道は竜ヶ岳から東へ下りて清滝へ下る時に横切る林道につながっているようだ。
なぜかここだけ咲いていたクリンソウ。

しばらく行って田尻の廃村跡。

廃村八丁を彷彿させる。
ようやく山道らしくなってきて、沢沿いを行く。

なぜか排気ガスのにおいが強くすると思ったら、モトクロスバイクの二人に出会った。高雄側からやってきたようだ。
歩き出して2時間少々、12 時過ぎに松尾峠に到着して、ここで昼食にした。

昼食後に今日の目的の朝日峯に向かう。峠からは少し林道。

少し行って林道からはずれて山頂へ向かう。

山頂まではほんの 10 分程度だが、自然林の非常に雰囲気のいい道だ。

1時前に朝日峯(688.1m)に到着した。

ここは展望が素晴らしい。
正面は比叡山。左には横高山と水井山。

京都市内の向こうは鷲峰山などの山城の山々。

松尾峠に戻って高雄へ向けて下山。松尾峠のお地蔵さん。

このあとは登山道で、2時頃に林道まで下りてきた。

沢の対岸にマタタビ。

不気味な不動尊。

この道は昨年、京都一周トレイルを伏見から嵐山まで行った時に間違って入り込んだ道だ。
清滝川の橋に到着したところで今日は解散ということになった。

皆さんは高雄からバスで帰られるので、一旦バス停まで行ってから、私はトレイルコースを沢池の方向に行くことにした。
沢池方向へ向かう林道はこれまで高雄に向かう方向しか走ったことが無いので、どうも雰囲気がしっくりこない。こんなに急だったのかという感じ。

バス停を出て 30 分くらいで沢池への道の分かれまで来た。

時間も時間なので、沢池へは向かわずにこのまま林道を進む。

下りに入ったらもっとしっかりした林道になるのかと思ったら、以外に山道っぽくなってきた。

しかしそれもわずかで、1時間足らずで住宅街に出た。

そのあとわずかで今朝バスで通った R162 に出た。
JR の花園駅まで歩こうと思っていたのだが、こういう道を歩くのはストレスが溜まるもので、バス停に何人かが待っておられるので時刻表を見たところ、四条烏丸行きの1時間に1本のバスが間も無く来そうな時間だったので、これに乗ることにした。
さて、今日の最大の収穫は実はコレだった。

昨年、横山岳で見かけたヤマシャクヤク。

どこで見かけたかはヒ・ミ・ツ!。
カテゴリー: 登山
大黒山
昨日は随行で湖北の大黒山へ行ってきた。
もちろん登るのは初めてで、これまでに山名すら聞いたことが無かった。
JR の余呉駅からタクシーで椿坂峠に向かう。
R365 は木之本と今庄を結んでいる谷筋の道だが、ここは柳ヶ瀬断層という活断層になっていて、断層の東側(大黒山方面)は傾斜が急で、西側はなだらかになっているという話をタクシーの運転手さんがしてくれた。
R365 と言えば思い出すのは今庄 365 スキー場。ここは昼間はスキーのみ(ボード禁止)というスキー場で、個人的には好みのスキー場だった。
椿坂峠は現在はバイパスのトンネルが通っているので、旧道で峠まで行くつもりだったのだが、旧道が通行禁止になっていて、トンネルを出て旧道と合流する所から歩くことになった。

峠まではゆるやかな登りで 20 分くらいだった。
峠にはバブル時代に別荘地として売り出されたとかいう名残がわずかに残っている。

峠のほんの少し手前から登山道が東に入っているが、道標などはまったく無い。このあたりは余呉トレイルというコースになっているそうだが、そういう標識は一切無かった。
登山道はいきなりの急登で始まるが、ちょうど登山道に沿って工事用のモノレールが敷かれていて、車道には車が2台ほど停まっていた。
登山道の溝に沿ってレールが敷かれているので、わずらわしいことこの上ない。
レールが手すりになって助かる場合もあるけれど、レールをまたいだりくぐったりと、素手だった私は早々に手が真っ黒になってしまった。

このコースは全般的にあまり展望が無かった。
たまに開けた箇所からは西側の赤坂山方面が望めたが、私にはどれがどの山だかさっぱりわからない。

傾斜は少し緩くなってきたけれど、レールはまだまだ続く。

もう山頂が近いというあたりまで登ってきたら、ようやくレールが終わった。座れる椅子が並んでいる。

ほどなく稜線の道に合流して、歩き出して1時間半ほどで大黒山の山頂(891.6m)に到着した。


まだ昼前なので、ブナ林を東峰に向かう。
久しぶりにギンリョウソウ。

一度目につくと、この後もしばしば見かけた。
このあと、送電鉄塔の整備の工事をしている人たちに出会った。例のモノレールで上がってきた人たちだった。
これは変わったブナの木。

このアングルで見ると2本の木に見えるけれど、反対側から見ると太い1本の幹になっていた。
ナナカマド。

大黒山から 30 分ほど歩いて、東峰で昼食にした。サルの群れがいたそうで、ケモノ臭がぷんぷんする。

来た道を引き返して、大黒山手前の尾根を南へ下る。分岐にはテープがあるだけで、道標は無し。

滑りやすい急な下りが続く。
奇妙な形の木が随所に現れる。

途中の展望エリアで東の方向を望む。鉄塔の左側は三周ケ岳?

3時過ぎに沢筋の林道のところまで下りてきた。
ウツギの仲間。

コアジサイ。

30 分ほどでバス停に着いた。すぐそばに八幡神社。

1日3本のコミュニティバスで余呉駅に戻った。

好天の土曜日にもかかわらず、他の登山者は誰一人会うことがなかった。
休日に山へ行くならこういう静かなところがいいけれど、いかんせん遠い。まさか一人で来てタクシーを使うわけにもいかないので、こういう機会でも無ければ来ることが無いという貴重な経験だった。
由良ガ岳
月曜日に続いて火曜日は由良川河口近くに聳える由良ガ岳へ行ってきた。
もちろん私は初めての山。
この日も暑い一日だったが、午後から日射しが弱まって、前日よりは多少はマシだった。
貸し切りバスで京都駅をスタートして、京都縦貫と舞鶴若狭道、綾部宮津道を通って、2時間半近くで上漆原の林道に到着した。

おそらくあれが由良ガ岳東峰。

すでに標高は 400m を越えているので、登るのはほんの 200m くらいだ。
舞鶴市が観光に力を入れているそうで、登山道は整備されている。

このあたりはタニウツギがたくさんあった。

まずは西峰を目指す。

歩き出して1時間少々で西峰(640m)に到着した。

天橋立が望める。

半島の先にあるのは一瞬、原発かと思ったが、京都府には原発は無い。関電のエネルギー研究所とのこと。

これはタニウツギの花が咲く前。

東峰に向かって少し行くとまた展望エリアがあって、足元に由良の街並みが見える。右は由良川の河口。

これはカマツカ。

整備された広場でゆっくりめに昼食をとった。

昼食後、20分ほどで東峰に到着した。

祠の手前には狛犬が左右に配置されている。
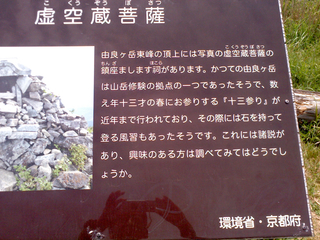
由良川の河口が広がっている。

若狭富士と呼ばれる青葉山の姿が美しい。

下山は北側の由良に向かう。
1時間20分ほどで無事下山した。

時間があったので、海岸の公園に立ち寄った。

このあたりは森鴎外の「山椒大夫」の舞台になったらしい。
海辺から由良ガ岳を振り返ってみる。

こうして見ると 640m もある山には見えない。
この講座は前日よりもレベルの高いクラスだったが、内容的にはずいぶんゆったりとした行程だった。前日よりははるかに楽で、私自身も楽しむことができた。
大和葛城山
月曜日は登山教室の随行で大和葛城山へ行った。
ちょうど昨年のこの時期にも別の講座で登ったが、同じルートで登って、ロープウェイの山頂駅で解散して、後は各自自由という行程になった。
前日のマラニックにも増して日射しの強い暑い日で、年齢層の高い講座で葛城山までの登りが大丈夫か不安だったが、昨年よりは人数が少ないこともあって、昨年ほど前後が開くことは無かった。
昨年は好天の日曜日だったので道が渋滞してバスが何時に着くかわからないという状態だったので、ロープウェイの駅まで1時間ほどかけて歩いたけれど、今回は月曜日なのでバスに乗ることができた。それでもバスは満員になった。
ロープウェイの駅を10時頃に出発。

山頂はすぐそこのように見えるが、登りは階段の連続でなかなか厳しい。

定番コースでくじらの滝へ。

階段をひたすら登る。

2時間半ほどの登りで無事山頂エリアに到着して、昼食にした。日射しは強いが空気は爽やかだ。
昨年もツツジはほとんど終わっていたけれど、今年はすでに完全消滅状態。

向かいは金剛山。昨秋にこの講座で行かれているのだが、私はその時はヘルニアで休んでいた。

このところ天気が良くても遠くは霞んであまりよく見えない。まだ黄砂の影響なのだろうか。

昼食後は葛城山頂へ。

午後1時過ぎに山頂(959.7m)に到着した。

大和三山を見下ろす。何度見てもどれが何山か覚えられない。

この後、ロープウェイの山頂駅まで行って解散となったが、3名の方が歩いて下りたいということで、私も歩いて下りるつもりだったので、一緒に下ることにした。
自然研究路を下って、昨年下りた道に途中で合流した。
途中でリスを見かけた。
展望エリアでロープウェイが通過していくのを眺めて、滑りやすい道を慎重に下った。

このところ快晴の日が続いているので、土が乾いて非常に滑りやすくなっている。
慎重に足を置いていたのだけれど、それでも左足を滑らせてしまって、バランスを崩したひょうしにそばにあった木に頭を打ち付けてしまった。
打っただけと思っていたら、少ししたら血がにじんできた。
ボクサーがよく試合で出血する、まぶたの上の骨の出っ張ったあたりを木に打ち付けたようで、同行の方に心配させてしまった。しかしケガをしたのが自分で良かった。
帰りのバスはちょうど数分前に出たばかりで、次のバスまでは50分ほど待たなければならない。
みなさんは売店で休んでバスを待たれるとのことだったが、私は昨年と同様に近鉄御所駅まで歩くことにした。
30分ほどで着くと思っていたが、35分ほどかかって駅まで歩いて、自動販売機でコーラを買って電車に乗り込んだ。
この日、履いていたのはもう3年ほど使っている重めのトレランシューズで、カカトが随分すり減っていて、ブロックが消えてきている。
今日のコースなら大丈夫だろうと思っていたが、下りの最後の方が滑りやすいということはすっかり失念していた。
このシューズはもう山で使うのは止めて、普段履きに格下げしようと思う。
堂満岳
今日は登山教室の随行で比良の堂満岳へ行ってきた。
久しぶりに正面谷を登って、気持ちのいい一日だった。
堂満岳は麓から見た姿が精悍な山だ。山頂付近はなかなかの急坂だが、危険な箇所はほとんど無い。
2年ほど前にも登山教室で別ルートから登ったが、個人的にはそれ以来の再訪となる。
イン谷口でバスを降りて、正面谷を詰めていく。

大山口で小休止して、堰堤をいくつか越えていく。

これはタニウツギというらしい。

左手から堂満谷が流れ込む。

いよいよ青ガレへ。

琵琶湖が足元に広がってきた。

青ガレが終わってもまたガレっぽいところが続く。

残念ながらシャクナゲはもう終わっているが、シロヤシロがいい感じ。

歩き出して1時間半ほどで金糞峠に到着。


峠から少し北西へ下ったところで少し早めの昼食にして、その後は芦生杉を眺めに行った。

金糞峠に引き返して、いよいよ堂満岳へ。
これはアカヤシオ?

上に上がるとシャクナゲも少しは残っている。

峠から 45 分くらいで堂満岳(1057m)に到着した。

朝方は稜線のあたりは雲に覆われていたけれど、琵琶湖がきれいに望める。

しばしの休憩を取って、東尾根を下る。
最初はなかなかの急斜面で、滑りやすい。
1時間半ほどかかってようやくノタノホリ。

ここは訪れたことがあるはずだが、もはやまったく記憶が無い。
岸辺から延びた木の枝にモリアオガエルの大きな卵の固まりが。

本数の少ないイン谷口からのバスのちょうど 10 分前くらいに無事下山することができた。
とても楽しい一日だった。
大谷山
昨日は登山教室の随行で野坂山地の大谷山へ行ってきた。
天気予報では午前中は雨の確率が高かったが、登山口までのアプローチで少し降られたくらいで、行動中はほとんど降られなかった。
ただし黄砂の影響などもあったようで展望はあまり得られなかった。
しかしこの地域独特のブナ林ではガスがかかった幻想的な風景が味わえて、まるで水墨画の世界に迷い込んだような雰囲気の一日だった。
マキノ駅からバスでマキノスキー場の温泉さらさで下車。

まずはゲレンデの斜面を登って行く。

先月の伊吹山と同様に、眼下に琵琶湖の風景が広がってきた。

登って行くとオオイワカガミがたくさん出てきた。

マムシソウも。

約2時間で寒風へ到着。

足元はガスに覆われている。

大谷山を目指して稜線を歩く。

歩き出して2時間半で大谷山(814m)に到着した。

下山は石庭下山口から石庭方面に向かって、704m 地点から不明瞭な稜線を南下する。
このあたりはまるで水墨画の世界だった。


滑りやすい道を慎重に下って、田屋城跡へ。



その後、車道をしばらく歩いて沢のバス停からバスに乗って、近江中庄駅から電車で帰ってきた。
このところの登山教室はあまり天候に恵まれていないけれど、雨の予報にもかかわらずそれほど雨には降られないという日が続いていて、これはこれで運がいいのかもと思ったりしている。
廃村八丁、品谷山、小野村割岳
中学2年の時になぜかワンダーフォーゲル部に入って山に登り始めた。
とは言っても山へ行くのはほぼ月1回の例会のみ。それも雨だと中止になるので、年間の山行回数は 10 回くらいだったと思う。
夏山は常念岳や白山に行ったけれど、普段行くのは京都の北山だ。
その頃のバイブルは『京都周辺の山々』というガイドブックだった。
このガイドブックで非常に興味をそそられたのが高層湿原の八丁平と土蔵の残る廃村八丁。
その頃の中学生にとっては京都の北山と言えども八丁平や廃村八丁は最果ての地だった。
幸い、八丁平へは行く機会に恵まれたけれど、廃村八丁は結局その後も足を踏み入れることの無いまま、今日まで過ごしてきた。
バス便はあるけれど、1日3本しかない。2時間近く乗らなければならないので、もし座れなかったりしたらそれだけで疲れ果ててしまいそうだ。
車で行けばいいのだけれど、京都市内を通過しなければならないので、帰りの渋滞を考えるとなかなか思い切れない。
しかしここ3年ほど近場ですっきりしたロングルートはかなりトレースしてしまった感があるので、これからは不便で辺鄙な所に進出するしかない。
と言うことで、長年の憧れだった廃村八丁へ向かうことにした。もはや土蔵は残っていないけれど、どんな雰囲気の所なのか、この目で確かめてみたい。
そう思って、覚悟を決めて車で出かけた。
家からほぼ2時間で登山口の菅原に到着して、8時半に歩き始めた。以外と寒い。ノースリーブのアンダーを着てきて良かった。

朽ちた道標で気分は上々。

廃村八丁までは楽勝と思っていたし、始めのうちは道もはっきりしていた。

しかし間も無く道は不明瞭になり、沢筋はかなり荒れていた。
今日のシューズは salomon の crossmax。このシューズはソールのブロックが硬くてしっかりしているので、通常の山道ならかなり安心して歩ける。
しかし沢筋の濡れた岩というような状況になるとこの特徴が逆効果になって、とにかくよく滑る。こういう特性がまだよくわかっていなかった頃、沢を渡るときに何気なしに出した足が滑って、激しく転倒したことがある。
沢を渡る時はとにかく慎重に足を出した。
テープを目印に進んだのだが、いつの間にやらルートをはずしていた。gps で確認すると、本来のルートよりも北に行きすぎているようだ。
斜面をへつって本来のルートに合流しようとしたが、急な斜面に行き詰まってしまった。テープも見あたらない。
少し戻って何とか下れそうな斜面をずり落ちて、沢に下りついた。

写真では何と言うことの無い斜面に見えるけれど、なかなか緊張を強いられる下りだった。
沢筋をつめて行ったが、本来のルートはさらにこの南側の稜線のようだ。しかし南側の斜面もなかなかの傾斜で手強そう。
このまま沢をつめると合流できそうな感じだったので先へ進んだところ、ようやく本来の道に出会えた。

ダンノ峠までは1時間近くかかってしまった。


ここからは八丁平を思い出させるおだやかな地形で、小さな沢を何度も渡りながら先へ進んだ。

突然、建物が現れたが、同志社大学の研究施設らしい。

ここから先はこれも印象に残る名称の四郎五郎峠へ向かう。しかし峠への取り付きはまたわかりにくかった。
廃村八丁への道はかなりしっかりしていると予想していたので、この状況はまったくの想定外だった。
ほどなく四郎五郎峠に到着。


つづら折れを下ってしばらく行って、10時8分にようやく廃村八丁へ到着した。
かつての建物の石の土台がいくつか残っている。

山小屋があるが、施錠されている。

そのすぐそばには土蔵の跡。

定住者があったのは昭和の初期までだそうだが、それにしてもこんな場所に定住者がいたというのは今の感覚では信じられない感じだ。
このあたりは森林資源が豊富で、地元の地域間の争いが絶えなかったらしい。
その時代は今のように電気、ガス、電話なども普及していないし、交通機関も限られている。そんな時代なら水には困らない場所で、金になる森林資源が身近にある場所に住もうという発想はあながち突飛なものではなかったのかも知れない。
ただ、冬の厳しさは相当なものだったようで、廃村になったきっかけも豪雪で集落が孤立してしまったことが大きな要因だったとか。
ここの廃村の土台の石組みというのは、城跡の石組みが残っているのを見るのとはまったく違った印象で、殿様の生活というのはどう考えても自分とはつながらないけれど、ここの人たちのかつての生活はどこかでわずかながらもつながっているのではないかと思わせる雰囲気を漂わせている。
丸太に腰を下ろしてジェルを補給して、品谷山へ向かう。
品谷山へは目の前の沢を渡らなければならないのだが、渡渉地点が見あたらない。仕方無く少し上流へ戻って、浅瀬伝いに渡れそうな所で渡ることにした。
石を飛ぶのは危ないので、多少の濡れは覚悟して流れの浅そうな箇所に足を置く。それでも案の定、足を滑らせて、転倒は免れたものの、シューズは流れに沈没した。
まぁこういうことはトレランでは覚悟の上だ。そのために濡れても冷えない、不快感の少ないソックスを履いてきている。
道は不明瞭だが、ほどなく沢が細くなって、自然と流れのそばを登るようになった。
今日は誰にも会わないと思っていたら、上から二人の男性が下ってきた。年は私よりは若そうだが、かなりのベテランという感じだった。
沢筋から離れて急な斜面を這い上がって、品谷峠へ到着。

ようやく道がおだやかになって、はっきりしてきた。稜線を行くようになったが、木が多くて展望はあまり無い。
品谷山(880.7m)へは11時前に到着した。


稜線をしばらく行くと、今日初めて少し展望の得られる場所に出た。見えているのは南の方角だが、どこの山かはわからない。

少し下ると十数人の中高年団体が上がってきた。
ダンノ峠への分岐点。

少し下ると今度は少し年代層の若い女性主体の10人ほどの団体が上がってきた。トップはいかにもガイドという雰囲気の男性。
佐々里峠手前には電波中継塔が立っていた。

品谷山を出て35分くらいで佐々里峠に降り立った。

道路を渡った先の道がよくわからなかったが、駐車スペースの奥から階段が上がっていた。
地図のルートより少し手前に小野村割岳への分岐が出てきたので、そちらへ向かう。

しかしすぐに元の道とまた合流して、その少し先にまた分岐があった。

ここからは杉の巨木がいくつかあるらしい。

12時を過ぎているので、こんな木に腰掛けておにぎり休憩にした。

ほどなく巨大杉。

雷杉の所には家族連れのような集団がいた。

この道は私の持っている登山地図では破線の不明瞭ルートになっているが、私の印象では実線表記の廃村八丁への道よりはるかにしっかりしている。天気さえ悪くなければ迷う心配の無さそうな道だ。
これはブナ?

小野村割岳(931.7m)には13時10分に到着した。


当初の予定では三国岳まで行って、久多へ下りて車道で戻る計画だったのだが、そちらへ行ってしまうと途中でショートカットできるルートが無い。時間的にもかなり厳しそうだ。
車道まで下りてしまえば暗くなっても大丈夫だろうが、今日はそこまでモチベーションが高くない。
まだ時間は残っているけれど、今日はここからすんなりと南へ下りることにした。
少し下った所で少しだけイワウチワ。

15分ほどでしっかりした道に出た。

地図では林道のような表記になっているので、車が通れるくらいの道かと思っていたのだが、実はどんでもなく荒れていて、元林道という方がふさわしい。手入れなどまったくされていない。

少し下ると変わった滝。

もう少し下るとまた滝。

さらに下るとゲートがあって、ここからは少しまともな道になった。

猟銃を持った人がいてちょっとびびったが、2時半過ぎに車の場所に戻ることができた。
今日は行動時間が6時間くらいで、距離も 20km 少々というところ。不完全燃焼と言えば不完全燃焼だったけれど、ルートが不明瞭なコースへ行く時はあまり距離は欲張らずに、堅実に歩くということを最重視した方がいいように思った。
比叡山北方稜線へ行った1回目もそうだったけれど、今日も結果的にはこれで良かったのだろうと自分に言い聞かせている。
帰りの車も恐れたほどの渋滞にはならず、5時過ぎには家に帰ってくることができた。
また車利用で残った宿題に取り組んでみようと思う。
瓢簞崩山
昨日、夕食を終えてくつろいでいたら、アルコールがまわったのか、練習会の疲れがどっと出てきた。
キャノンボールを終えた後よりもひどかったくらいで、風呂でも椅子に腰掛けて、しばらく一息いれなければならないくらいだった。
しかし翌日には登山教室の仕事が入っている。
何があっても行かない訳にはいかないので、風呂から上がったら早々にふとんに入った。
疲れすぎるとなかなか寝付けないという症状が少し出たけれど、幸い朝起きた時には疲れはほとんど消えていた。
今日の行き先は京都北山の瓢簞崩山(ひょうたんくずれやま)。
山名は中学生の頃から知っていたけれど、登ったのは何と今日が初めてだった。
天気予報通り、朝から本降りの雨で、気分は重い。たまに雨が弱まって日射しが一瞬差すこともあるが、またすぐに本降りになる。
ただ、午後には回復するとか。
9時半過ぎに歩き出した時には雨は小降りになっていたが、雨具は上下とも着たままにした。こういうことを想定して、涼しい薄着のウエアにしておいた。

江文神社の境内で少し時間を取ってから、一周トレイルルートで江文峠に出る。
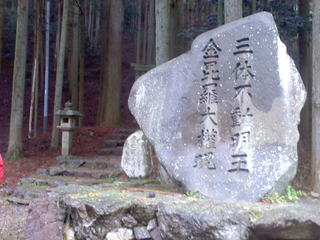
ここで読図の勉強をする。地図と磁石で正しい方向に歩く方法を学んだ。
私自身はこれまでの山歴の中でこういう方法で歩いたことはほとんど(まったく?)無い。
なぜならこういう技術が必要になるような不明瞭なヤブ山歩きというものをほとんどやってこなかったからだ。
山スキーでは大切な技術なのだが、私が本格的に山スキーをやり出した頃にはすでにハンディ gps が登場していて、私も早々に入手した。
地図と磁石で正しく歩く手法で最も重要なのは、現在地点を正確に把握するということなのだが、実はこれが非常に難しい。
道標がしっかりしているルートでは道に迷うようなことは少ないし、視界が悪くてうっかり変な方向へ行ってしまったような時は、おかしいと気が付いた時には現在地点を知ることなどもはや不可能に近い。
こういう技術は登山のイロハのようなもので、必ず身につけておく必要があるとは思うが、現実的には今なら各自が gps を持って、gps の使い方に精通しておくのが一番安全だと思う。
金比羅大権現の前で車道を渡って、静原へ行く道から分かれて瓢簞崩山への道に入る。最初はなかなかの急登。

最初に目標設定した 471m ピークに到着。雨はほとんど止んでいる。

目標を再設定して、さらに進む。
ちょっとした峠のような場所ではミツバツツジとヒカゲツツジ。


寒谷峠には 12 時半に到着。

それから 10 分ほどで瓢簞崩山(532m)に到着して、ここで昼食。

真正面には比叡山が望める。

昼食後はほぼ南の方向に、稜線伝いに下って行く。
横高山と水井山がきれいに望める箇所があった。

少し先が二本松。

ハルリンドウ。

京都の街が足元に。

日曜日だと言うのに今日は誰にも出会わない。
このあたりはマツタケ山のようだ。


ほどなく崇道神社に下りてきた。


ここで解散して、地下鉄の国際会館へ行く人と京福の三宅八幡へ行く人に分かれたが、私は高野川沿いを出町柳まで歩くことにした。
京都生まれの京都育ちで、賀茂川沿いは通勤ランも含めて数え切れないくらい歩いてきたが、高野川沿いというのはこれまで歩いた記憶が無い。車道を車やバスで走ったことしか記憶に無い。
高野川沿いになってもなかなか河川敷に下りられず、歩道も狭くて閉口したが、修学院を過ぎてしばらく行ったあたりでようやく河川敷に下りることができた。

三宅八幡から 50 分くらいで出町柳にたどり着くことができた。朝方とはうって変わって、強い日射しが川面を照らしていた。
霊仙山
柏原駅の前にあった霊仙山への標識に従って南へ向かう。午後2時半少し前。
もし時間がかかりそうだったら途中で引き返すつもりだ。
中山道を横切り、信号の無い国道を渡り、名神高速の高架をくぐって、しばらく車道を進むと、登山道入り口の標識が現れた。

この時間から標高 1000m を越える山に向かうのはちょっと無謀かもと思った。このあたりは標高 200m くらいだ。
車道を行くのか山道に入るのかよくわからない箇所があったが、朽ちた標識に気が付いてしばらく車道を進むと、次第に山道になってきた。
一合目までは駅から 40 分くらいだった。

ここまでの道は緩い登りで時間が稼げた。
沢筋の樹林帯で少し暑くなってきたので、ライトジャケットを脱いで、ジェルを補給した。
スタートしてほぼ1時間で二合目に到着。

しかしここで道が尾根筋になって、また西から強い風が吹いてきた。
三合目あたりではまたライトジャケットを着ることになってしまった。

道ははっきりしていて迷うような心配は無いけれど、やはりと言うべきか、時間がかかっている。
四合目は午後3時50分。

ここには朽ちた避難小屋があった。

上に上がるにつれて風が強くなってきた。
五合目はちょうど午後4時だった。

2時間くらいで頂上にたどり着けないかと思っていたが、どうもそれは厳しそうだ。
しかしここまで来たらもう前に進むしか無い。引き返すという気持ちはすでにまったく無かった。
順調に六合目を通過。

七合目は午後4時15分。

スタートしてほぼ2時間でようやく八合目まで来た。

ここを越えると高い木が無くなって、頂上エリアの雰囲気になってきた。
しかしおかげで風がさらに強くなり、しばしば身体を持って行かれるくらいの強風にさらされるようになった。
ザックの中には軽いベストと雨具の上下が入っているが、この強風の中ではザックを開けてごそごそする気にはなれない。うっかり飛ばされてしまいそうだ。
前方に避難小屋が見える。

あまりにも風が強いので、地図を出して現在地を確認する気にもなれず、何となくもうあと少しかなと思っていた。
八合目から 10 分少々で避難小屋へ。

この先が頂上かと思ったのだが・・・

登り着くとそこは経塚山で、頂上はさらにその先だった。

最高地点(1098m)は霊仙山の少し東側にあるらしい(上の写真の背景の山)。しかしもはやここに立ち寄る余裕は無い。
一度少し下ってから、足元に石灰岩の突起がたくさんある歩きにくい斜面を、強風にあおられてふらふらしながら登って、午後5時直前にようやく霊仙山の山頂(1084m)に到着した。

もうあたりはすっかり夕刻の雰囲気で、展望を楽しむ余裕も無く、写真を撮ったら早々に下山に向かうことにした。
当初は醒ヶ井の方に下りようと思っていた。こちらに向かうと早めに車道に出られそうなので、車道に出てしまえば暗くなっても何とかなるだろうという目論見だったのだが、そちらへ向かう道がわからない。
少なくとも山頂からその方向には道らしきものは見あたらない。
私が持っている古い地図では来た道を少し北に戻った所から西に分かれているのだが、そういう標識は見あたらなかった。
と自分では思っていたのだが、帰ってから写真を見てみると、経塚山頂の標識に『落合・榑ヶ畑(くれがはた)』とあって、実はこれがその方向だったのだ。
山頂と経塚山の間に下りた時に、その方向に向かうかすかな踏み跡があって、少し行ってみたのだが、はっきりした標識が無かったので、この時間にこの状況で不安な方向に向かうのは危険と思って、その時点で来た道を引き返す決断をしたのだ。
登りが2時間半ほどだったので、道の状況を考えると2時間はかからずに下山できるだろうと思った。6時半くらいまでならライトを点けずに歩けると思ったので、その頃には登山道は終わっているはずだと思った。
とにかくこの強風から一時も早く逃れたいと思った。それには未知の不安な道を進むよりも、来たばかりの記憶の残る道を戻る方が、精神的にも楽だと思った。
八合目まで戻ると吹きさらしエリアからは脱出できた。しかしまだまだ風は強い。
時間はすでに午後6時前。何とか暗くなる前にしっかりした道まで戻りたいと思って、走れるようなところは走った。
ただ、結構疲れているはずなので、ミスで転倒したりしないよう、気持ちを落ち着けるつもりでジェルを補給した。
6時25分くらいにしっかりした道まで戻ることができた。
メモしてきた電車の時間を見ると、次の電車は6時55分くらいだ。何とかこの電車に間に合わせたいと思って、車道に出てからはずっと走った。
柏原駅に帰り着いたのは6時45分だった。

何とか暗くなってしまう前に戻ってくることができた。
このところ登山教室の仕事が早く終わると、個人的にアフターを楽しむ習慣になってしまっているのだが、この日のアフターはいささかやり過ぎだと思った。
こういうことはもう少しほどほどにした方が良さそうだ。
清滝山
月曜日は登山教室の随行で滋賀県の清滝山へ行った。元々は4月4日の予定だったのだが、雨のために一週間延期になった。
『清滝』という名前を見ると京都の人間は前日に行った愛宕山麓の清滝を思い出すのだが、実は東海道本線を隔てて伊吹山の南側にある小さな山だった。
このところの登山教室は天気予報では晴れなのに、実際は曇りで気温が低い日が続いていたが、この日は陽が差して好天になりそうだった。ただし冷たい風が吹いていたので、ライトジャケットを着たままで歩き出した。
スタートは東海道本線の柏原駅(かしわばら)。

中山道の宿場町として栄えた街だそうで、なかなか味のある街並みが残っている。


中山道からそれて登山口へ向かうと、目の前に清滝山が見える。

右前方にはつい先日登った伊吹山。

清滝寺の参道はまだ桜がきれいだ。


徳源院には京極家の墓所がある。

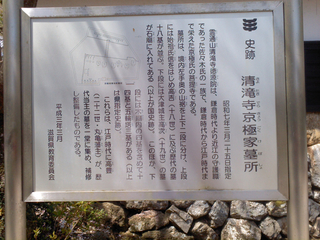
境内の道誉ざくらがみごとだったが、ピークは1週間前くらいだっただろうか。

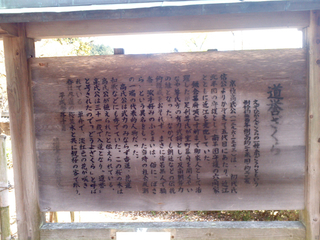
いよいよ登山道に入る。滑りやすいかなりの急登がしばらく続く。

登り始めて 20 分くらいで清滝山の山頂(438m)に到着した。山頂には NHK の電波塔が建っている。


北には伊吹山がど〜ん。

南は霊仙山と鈴鹿の山(鈴北岳?)。

柏原の街並みが足元に広がっている。

昼食を済ませて下山に向かう。
稜線にはミツバツツジ。

下山路は階段。

下山した場所は実は清滝寺のすぐ近くで、『清滝のイブキ』という大きなイブキの木がある。


このあと、一部の人たちは京極家墓所の拝観に向かわれて、他は北畠具行の墓に向かう。
再度ちょっとした山道へ。

フェンスを開けて少し登ると北畠具行の墓がある。

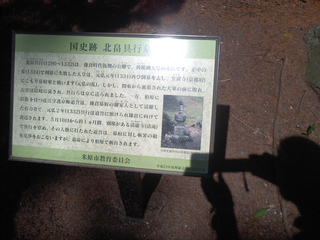
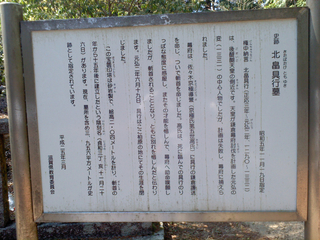
山道を少し下ると中山道に合流した。

ここから中山道をゆっくり 20 分ほど歩いて、柏原駅に帰り着いた。
しかしまだ2時半にもなっていない。
この日は早く終わることが想定されたので、時間があれば霊仙山を目指してみようかと企てていた。
しかし地図にルートを引いてみると、ピークまで 10km くらいある。下山も含めるとほぼ 20km だ。
清滝山から眺めた霊仙もかなり遠かった。
どうしようかと迷ったが、天気も良く、このまま帰るのはあまりにもったいない。
中山道を歩いて醒ヶ井までというのも頭に浮かんだが、元々あまり文化的な人間では無いし、中山道の知識があるわけでもないので、やはり行けるところまで行ってみようと思い、一人で霊仙に向かうことにした。
