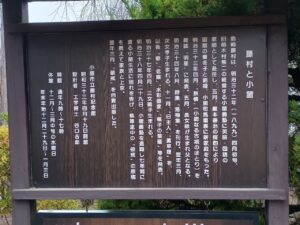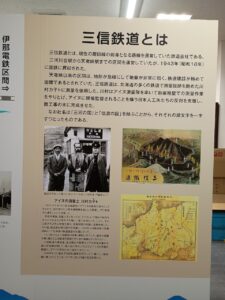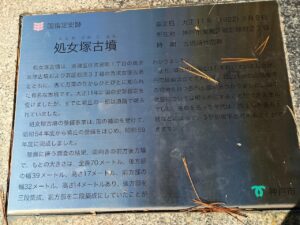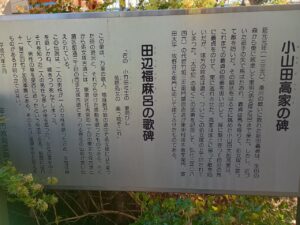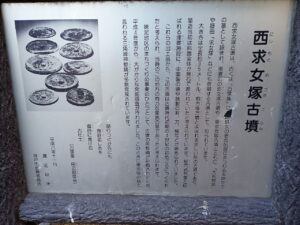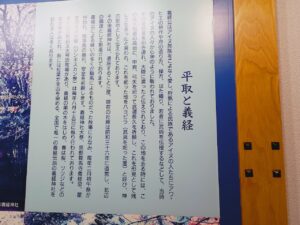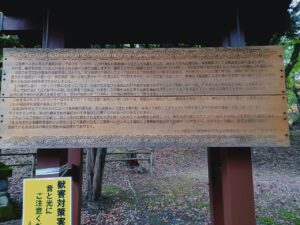12/26(金)は北陸回りで帰阪する。
朝起きたらまず外の天気を確認した。幸い、小雨程度で雪は降っていなかった。
朝風呂を楽しんでから無料サービスの朝食をいただいた。パンはここで焼いている感じで、暖かさが残っていてサクサクしておいしかった。
まずは直江津へ。

乗り継ぎが40分ほどあるので、ホームの待合室に入った。風が強くて寒い。しかし待合室は暖房は入っていない。
まずは富山県の泊まで。

日本海の波がすごい。

しばらく進むと長いトンネルに入る。このあたりは高速道路もトンネルだらけだ。
何と、トンネルの中に駅があった!! 筒石駅という駅で、長い階段を登ると地上の改札口に出るらしい。鉄道ファンには有名な駅らしい。日本海まで出ると筒石漁港がある。
泊で金沢行きに乗り換えて富山に向かう。

富山ではかなり混んでいた。

富山ではぜひ海鮮を食べようと思っていたので2時間ほど時間を取っている。
ちょうど昼時で、改札の近くの店は行列になっていたので駅を出て、近くのビルの食堂街の店に入った。
普通の海鮮丼とはちょっと違う盛り付けで、ご飯の上ににぎり寿司のような形状のネタが並べられていて、どれも新鮮で品質が良く、とてもおいしかった。
これまでに北海道でも何度か海鮮丼を食べたが、それらと比べてもいちばん美味だった。もちろんビールも。
富山からは新幹線とサンダーバードでサクッと帰る。
幸い、これまで列車の遅延はなく、このあとも予定通りの運行だそうだが、サンダーバードが湖西線強風のために米原経由になり、京都着が30分ほど遅れると案内されていた。
予定の新幹線に乗り込む。

急に雪が舞ってきた。

立山連峰はまったく見えず。
これまでに旅は何度も行っているが、これほど天気に恵まれなかったのは初めて。八ヶ岳も浅間山も立山も、いずれもまったく見ることができなかった。
ただし大雨や大雪、強風に見舞われることは無かったので、最悪というほどではなかったと思う。