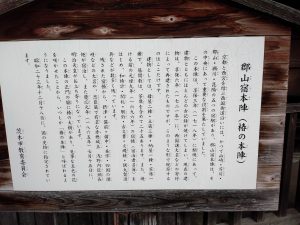個人練習に限界を感じてスキースクール のパーソナルレッスンを受けることにした。
3/27 の午後に出発して、白馬方面へ行った時の定宿のサンサンパーク白馬へ。

3/28(月)はエイブル白馬五竜スキー場でパーソナルレッスン。
五竜スキー場は 30 年ほど前に職場の同僚と毎年2月にスキーに行くということを5年ほど続けた。その後はゲレンデスキーから離れてしまって、十数年前に一度この時もプライベートレッスンで来たきりで、それ以来ということになる。

上部は強風のためにリフトが動いていないとのこと。今日はレッスン目的なので問題無し。
しかしここから見える左側斜面のハゲは雪崩の跡では?

すごい全層雪崩の跡。普通、雪崩は午後の気温が上がった時間帯が多いので、スキーヤーが巻き込まれたりしたのではないかと思ったが、スクールのコーチの話では早朝に発生したとのこと。早朝は一般的には一番雪崩の発生しにくい時間帯なのだが、非常にラッキーだったというほかない。
スキー場のゲレンデでも雪崩が発生することはあるということはわかっているし、何年か前に栂池で雪崩が発生して犠牲者が出たこともあった。しかしこんな激しい雪崩の跡をスキー場で目の前に見たのは初めてだった。
温泉は八方の倉下の湯へ。ここはお気に入り。

今日はザ・ビッグ白馬店へは行かずにコンビニで食材を買って、またサンサンパーク白馬に戻った。