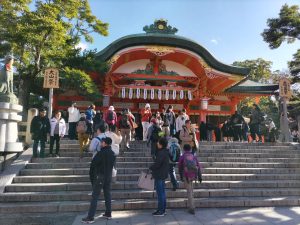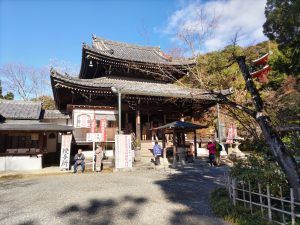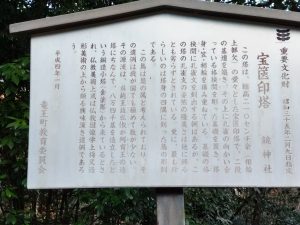大峰奥駈道はかなりの部分を歩いている。テント泊で全行程走破も一時は本気で考えたけれど、もはやそれだけの体力も気力も無いが、やはり全部歩いてみたいという気持ちは残っている。
先日、玉置山からの南部を歩いて、残る大きな部分は奥守岳から笠捨山で、ここは交通機関の便が極めて悪いのでなかなか実行できないでいた。
やるなら前鬼から稜線に出て行仙岳から下北山村に下りるくらいしかなさそうなのだが、あまりにも交通の便が悪くてとても思い切れない。
そこで苦肉の策として釈迦ヶ岳の太尾登山口から釈迦ヶ岳をトラバースして稜線に出て、涅槃岳まで日帰りピストン。そして後日、行仙岳から涅槃岳まで日帰りピストンというのが何とかなりそうなアイディアと考えた。
ただし太尾登山口から涅槃岳までは片道 10km 以上あって、おまけに復路が登り基調になるので簡単ではない。
やるならこれしかないと思って、11/26(日)に決行することにした。
家から3時間少々かかって太尾登山口まで走った。前回来た時もそうだったが、今回も7時半過ぎに到着した時はすでに駐車スペースが満杯で、手前の横のスペースに停めた。
準備を整えて8時前に出発した。相変わらず「熊出没注意」の看板が置いてあるが、今日は熊スプレーを持ってきている。

稜線に上がると目指す方面が見えてきた。ただし涅槃岳がどのあたりかはわからない。

30分ほど登ると釈迦ヶ岳と大日岳が見えてきた。

目指す稜線を眺める。涅槃岳はどれ?

さらに登ると深仙の宿が見えてきた。この時はすぐに行けそうに見えた。

出発して1時間足らずで古田の森。ここは標高 1618m で、涅槃岳(1376.2m)より高い。

しばらく行くと千丈平。水面は凍っていた。

出発して1時間15分ほどで神仙の宿への分岐に到着した。ここからは釈迦ヶ岳へのルートからはずれて右に向かう。

こちらに入ると一気に道の状態が悪くなったのでポールを出した。以前に反対向きに歩いたことがある。
神仙の宿に到着した。分岐から25分程度だったけれど意外と疲れた。

きれいに手入れされている感じ。

よく見たら扉が開けられそうだったので中を覗いてみた。

この時、涅槃岳まではムリなんじゃないかと感じたが、とにかく前に進む。
釈迦ヶ岳の東側の壁はすごい迫力。

大日岳の麓から大日岳を見上げる。

行場に興味はあるけれど高齢者の単独行なので万が一にも事故を起こしてはならない。
それよりも出発してからすでに2時間が経過している。地図を見るとまだ半分も来ていない。往路のタイムリミットを4時間と想定していたが、どう考えても5時間はかかりそうだ。しかも復路が登り基調になるのでそれ以上の時間がかかる。
ここまでがそれほど遅かったわけではないので、計画が甘すぎたようだ。
せめて地蔵岳まででもと思ったりもしたけれど、以前に奥守岳から嫁越峠を眺めた時のことを思い出して、またそれの再現になるだろうと思った。
それくらいならここで引き返して釈迦ヶ岳にでも登った方がすっきりするような気がして、ここで戻ることにした。それほど悩むこともなかった。
神仙の宿を過ぎて釈迦ヶ岳への稜線を登る。写真ではよくわからないが岸壁の右の方に穴がある。これが都津門。
そこに行くだけでも命がけだが、修行の人たちはどうやってあそこまで行くのだろうか。

左の方に古田の森が見える。

あと少し。

10時52分、釈迦ヶ岳山頂(1799.9m)に到着した。

釈迦如来像のそばにある一等三角点。

山頂から西の方面のパノラマ。
山頂は風が冷たいので少し下りたところでおにぎり休憩にした。
もうちょっと下ると水場があった。ここの水場に水が流れているのは初めて見た。

あとは往路と同じ道を淡々と下って、12時34分に登山口に下山した。

帰りは google のナビが京奈和道の渋滞をうまく避けてくれて、5時前には家に帰り着くことができた。