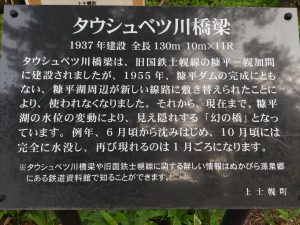7/23(日)はいよいよニペソツに向かう。
朝、起きた時、顔が少しむくんでいた。昨日のトムラウシの疲れだと思う。できれば今日は休養日にして明日に登れたら良かったのだが、天気予報では明日から天候が崩れるらしい。今日、行かざるを得ない。
12時間くらいを想定して早めに出ることにする。
3時50分に出発した。樹林帯はまだ薄暗いのでヘッドランプをつけた。

登山路の標識の距離表示は実際よりかなり長めになっていることが多いのだが、昨日のトムラウシもここもわりと正確だった。
30分ほど荒れた林道を歩いていよいよ登山路に入る。明るくなったのでヘッドランプをはずした。

明らかに昨日の疲れが残っているのでとにかく堅実な歩きを心がけた。
少し進むと足元がじゅくじゅくになってきて、進むのに苦労した。たまらずポールを出した。
そんなところを30分くらい登っただろうか、陽が上がってきた。

ゴゼンタチバナ。

3時間ほど登ったところでニペソツが見えた。

山頂ははるか彼方。はたしてあそこまでたどり着けるだろうか。不安が頭をもたげた。
平坦でぜんぜん標高の上がらない地形がしばらく続いた。
ミヤマアキノキリンソウ?

チングルマとツガザクラ?

エゾツツジ。

稜線への最後の登りにさしかかってきた。ザラザラの急斜面を上るとロープが出てきた。

このロープ、結び目がほとんど作られていないので持ちにくい。
8時前、ようやく稜線に出た。ここまで4時間以上かかった。

ここでおにぎり休憩にした。
それにしてももうかなり疲れている。今、登ってきたガリーはかなりの急斜面で、むしろ下りの方が危ない。もし足を滑らせたりしたらあんなロープではとても止められないし、かなり下の荒れた斜面まで滑落してしまうだろう。

今なら疲れているとは言ってもまだ多少の余裕はあるので何とか下りられると思うが、山頂まで行ってクタクタになって戻ってきたらはたして無事下りられるだろうか。そんな不安が頭をよぎった。
敗退?
しかし今日、ここで敗退したらもう再挑戦は無いだろう。それにすでに標高 1800m まで来ている。
不安を抱えながらも先に進むことにした。
イワブクロ。

少し行ったら何張りかのテントがあった。ここだと水を担ぎ上げなければならないので大変だろうと思う。

ウサギギク。

このあと天狗平でルートがわからなくなって何度も行ったり来たりしてしまったが、実は道標の見方を間違っていて、それに気付いてことなきを得た。
少し下ってからまた登り返す。いよいよ最終盤に近づいてきた。
最後に下りがあるというのは知っていたのでさきほどの下りがそうかと思っていたら、実はもっと大きな下りが待ち構えていた。おまけにこの頃からガスが出てきて先が見えなくなってきた。

最低鞍部にチシマノキンバイソウ。

最後の登りは苦しかった。ガスが切れて山頂が見えたが、このあと山肌をトラバースして右側から登り上げる。

10時12分、念願のニペソツ山の山頂(2013m)に到着した。

山頂からのパノラマ。
山頂でようかんを補給した。
イソツツジ?

15分ほど休憩して下山にかかる。あのガリーを下るまでは安心できない。
登り返しも何とかクリアして山頂を振り返る。

天狗平からのパノラマ。
天狗平でカロリーメイトを一つ食べて、いよいよ懸案のガリーを下る。

ロープ斜面もさることながら、その下のザレた場所もかなり緊張した。
危険箇所は脱したもののまだまだ先は長い。往路で山頂を眺めた場所からもう一度振り返る。

あとは淡々と樹林帯を下るだけ。
行きは気がつかなかったが三条沼という沼があった。

午後3時12分、ようやく林道まで戻ってきた。

そして登山口に戻ってきたのは午後3時40分だった。想定通りのほぼ12時間行動だった。

疲労感がいっぱいでうれしいという気持ちはあまり湧いてこなかった。うれしいというよりも「やれやれ」という安堵感が大きかった。
そして、こういう長時間行動の山行きはもうこれが最後になるのではないかと思った。
ずっと頭の隅にシコリのように引っかかっていたニペソツに登ることができて、肩の荷が下りたような感覚だった。
後片付けを済ませて幌加温泉に向かったが、なぜか営業していなかった。
仕方なく南に向かって、糠平温泉で適当な温泉を探した。
ここでもネットの情報で気軽そうな温泉はどういうわけかそこに行っても温浴施設のようなものが見当たらず、結局表通りに面した中村屋という旅館に入った。

いいお湯でした。
明日は休養日のつもりなので昨日行った上士幌のセブンイレブンで食料を買って、その近くの道の駅に車を停めた。