先の日曜日(6/18)は随行で有馬三山へ行ってきた。
有馬三山は個人的には今年の四月末に歩いた。
有馬三山だけなら距離が短すぎるし、かと言って六甲の稜線まで出ると結構な時間がかかりそうなので、どういうコース設定になるのだろうと思っていたら、有馬口駅から鬼ヶ島を経由して、有馬三山を上から下ってくるというルートだった。
集合は神戸電鉄の有馬口駅。

梅雨入りしてから一週間以上たっているけれど、ずっと晴れの日が続いている。
少し住宅街を歩いて水無川に合流。

私自身はこの道は初めて。登山地図にも記載されていない。
沢筋から分かれて稜線になるといきなり急登が続く。とても「ビギナーのための・・・」というタイトルのコースとは思えないが、みなさん慣れた方ばかりなので、特に問題も無く高度を上げた。
鬼ヶ島山頂直下にはイヌガシの巨木。

そして鬼ヶ島山頂(580m)。展望は無し。

さらに急なアップダウンを繰り返す。

地図には記載されていない水無山。

そしてようやく高尾山(739m)へ。

ほどなく有馬三山から極楽茶屋への道に合流して、ちょうどお昼に有馬三山の湯槽谷山(ゆふねだにやま 801m)に到着した。

ここで昼食にして、午後は北に向かう。
急な階段をしばらく下って、少し登り返して灰形山(619m)。

ここからは六甲の主稜線がよく見える。鉄塔が建っているのは最高峰。

落葉山(533m)に到着して有馬三山縦走は完了した。

落葉山のすぐそばに妙見寺。

午後2時頃に有馬に下山して、解散となった。
解散後の温泉を想定しての時間配分だったと思うので、私も温泉に入って帰るつもりだった。
休日の有馬温泉は混んでいるのはわかっていたけれど、日曜日の夕方になると混雑もましになるという話も聞いていたので、まずは金の湯へ行ってみたところ、待ち時間 10 分とのこと。
あきらめてまだ入ったことの無い銀の湯へ向かった。
途中に極楽寺。

銀の湯はすぐに入れるけれどかなり混雑しているという話で、雑踏嫌いの私はもう諦めて帰ることにした。
坂道を下っていたら、下から講座のお客さんの四人が上がってくるのに出会った。彼女たちは「かんぽの宿」に行くとのこと。温泉街の南の端の方なので、空いていることを期待して私もご一緒させてもらうことにした。
坂道と階段を上がってようやく「かんぽの宿」に到着。「かんぽの宿」なんて名前なら安いのだろうと思っていたら、何と入浴 1000 円!!
しかしここまで来て入らずに帰るわけにもいかない。
期待以上に空いていたのは良かったけれど、水風呂も無く、あまり長く居ることはできなかった。
まぁでも空いていたので良かった。
その後、みなさんとおいしいビールを一杯呑んで、電車で帰るというみなさんと分かれて私はバスで宝塚に出て、まだ薄暮が残る時間に帰ってきた。
カテゴリー: 登山
横高山、水井山
水曜日(6/14)は京都一周トレイルの講座の随行で奥比叡の横高山、水井山を歩いてきた。一周トレイルコースの中では最も標高の高いエリアだ。
先月、横川で終わってから歩いて下山した道を逆に辿って、登山口のバス停から横川に向かった。

比叡山のトレイルレースのコースを辿ってせりあい地蔵に向かう。

バス停から 45 分でせりあい地蔵に到着。なかなかの登りで、汗をかいた。

ここから 10 分少々で横川のバス停に到着した。

みなさんはバスでここまで来られて、せりあい地蔵に向かって歩き出した。
一人だと気付かないけれど、コアジサイ。

タツナミソウ。

せりあい地蔵でトレイルコースに合流して、急登を登る。

10 分ほどで横高山山頂(767m)に到着した。

一休みして、水井山に向かう。

11 時半過ぎに水井山(793.9m)に到着して、ここで昼食にした。一周トレイルコースの最高標高点。
あとは下山路で、仰木峠へ。

義経も通ったとか。

今日は空気の澄んだ快晴なのだけれど、コースはずっと樹林帯で展望の得られる箇所がまったく無い。
これではもったいないということで、時間もあるので少し北に登って展望場所に寄り道した。
ずっと向こうに見えるのはつい先日歩いた鈴鹿の御池岳から藤原岳の稜線。

東海自然歩道から分かれて戸寺へ下りる通称ボーイスカウト道に入る。

バス停に出る手前でまたちょっと寄り道して、惟喬親王の墓へ。


2時半頃、戸寺のバス停で解散となった。
大津の坂本にお住まいの講師の先生は仰木峠に登り返して自宅まで歩いて帰るとのことだったが、私は今日は早めに帰りたかったので、次のバスで真っ直ぐ帰った。
鈴北岳、御池岳、藤原岳
このところまともな山登りに行っていないという気持ちが心の底に淀んでいた。
この週末は今月で唯一、土日で出かけられる日だったのだけれど、梅雨入りしてしまって天候が不安定。
本当なら雪のある山へファストパッキングで出かけたいところなのだが、この天候では高山ではさらに不安定だろう。
仕方無く日帰りエリアでそこそこ満足感が得られそうな所ということで、最終的に鈴鹿を選んだ。
このあたりは高校生の時に友人と二人でテントを担いで歩いたことがある。しかしその頃の記憶はもうまったく無い。
覚えているのは、道がよくわからなくて1日目は水の無い場所に泊まらざるを得なくなり、わずかな水でフリーズドライのチャーハンを食べたことくらいだ。
その頃は鈴鹿にテント泊で行くというのはなかなかの大仕事だったのだけれど、今日は登り口の鞍掛橋まで家から車で1時間半足らずで着いてしまった。

堰堤に掛けられた脚立を登る。

私の持っている古い登山地図にはここから鈴北岳へ登る道は御池谷をつめるルートしか無いのだけれど、今は尾根を登って鞍掛峠からの稜線に上がる道があるようで、こちらの方が一般的になっているようだ。
御池谷をつめるルートは難路になっている。おそらく大水などで荒れているのだろう。昔来た時はこの沢ルートを上がったような気がする。

沢の横の平坦な道を少し行くと、いきなりロープのたらされた急登が始まった。

石の出っぱりや木の根をつかんだりしながらぐいぐい上がる。雨の日だったら登れない(下れない)だろう。
しばらく登ると送電線の鉄塔に出会った。

もともとは鉄塔の巡視用の道だったのではないかという気がする。
向こう側の斜面に見えている R306 は今は通行止めになっていて、三重県側には行けない。
一気に高度が稼げて、鞍掛橋の標高 425m から稜線の約 1000m まで 50 分ほどで上がることができた。

鞍掛峠からの道の合流地点はテープ印はたくさんあったけれど、標識はまったく無かった。
急に開けて、気持ちのいい山稜になった。ここまで来ると人が多い。鈴北岳はもうすぐ。

鈴北岳(1182m)には8時 20 分。出発して1時間 10 分ほどで到着した。

標識の向こうの山は伊吹山。
御池岳はすぐそこに見える。

鈴鹿最高峰の御池岳(1247m)には8時 47 分に到着した。

展望も無いので早々に先へ向かう。
しっかりした道標に導かれて、コグルミ谷からの道との合流地点。

ここから先はまた静かになって、アップダウンの少ない樹林帯の道を白瀬峠へ。

突然視界が開けたと思ったらまたもや送電線の鉄塔で、ここには頭陀ヶ平という三角点(1143m)があった。

振り返ると御池岳。

またもや樹林帯を淡々と進んで、分岐を少し西へ行って天狗岩(1171m)。

ここで今日初めて腰を下ろしておにぎり休憩。藤原岳ももう近い。

視界が開けて、藤原小屋が見えてきた。このあたりまで来るとまた人が多くなった。

2年前に随行で来た時は天気が悪くて藤原岳山頂へは行けずに、この小屋で昼食をとって下山した。
藤原岳(1140m)には 10 時 50 分に到着した。出発してから3時間 40 分。思ったより早かった。

あとは来た道を戻るだけの消化試合。あまり大きな登り返しが無いのが助かる。
帰りは御池岳はカットして沢筋の道を行く。

しっかりした道標が立っていたので安心して進んだのだが、どうも様子がおかしい。
案の定、沢筋はすぐに行き止まりになった。

どちら側に上がったらいいのかわからなかったので、斜面を見てみると右岸(左側)に這い上がっている痕があったので、そこを上がってみた。
しかし道は見あたらず、どうも反対側が正解のようだ。
一旦下りて、うろうろしながら這い上がれそうな場所を見つけて、今度は左岸に這い上がった。少し登ったら踏み跡が見つかった。
しっかりした道標が立っているわりにはずいぶん荒れた道だ。ほとんど人が歩いていない感じ。石もコケがびっしりとついたままで、歩かれた痕跡が無い。
想定外の不明瞭な道だったけれど、無事、行きに通った分岐に合流した。

この先は行きに確認していた不明瞭な踏み跡で少しショートカット。

鈴北岳は山頂をカットするトラバース道があったけれど、もう一度山頂に出てどら焼き休憩にした。

鈴北岳から 50 分ほどで無事下山することができた。まだ午後2時前だった。
若干もの足らない感じは無きにしもあらずだったけれど。このところ溜まっていたストレスは解消できたかなという気はしている。
矢田丘陵のち烏土塚古墳
月曜日(6/5)は登山講座で矢田丘陵へ行ってきた。矢田丘陵は昨秋に法隆寺から自宅まで走っている。
朝から快晴。近鉄郡山からバスで矢田寺前へ。

坂道を上がってアジサイで有名な矢田寺(金剛山寺)へ。ただし今日は中には入らない。

寺の北側の山道に入る。

所々に石柱がある。

歩き出して1時間くらいで矢田山(340m?)に到着。

展望デッキへ上がる。

生駒山がくっきり。

矢田峠に下りて、南へ向かう。

そして松尾山手前の国見台展望台で昼食。

ここから奈良方面の展望は素晴らしい。

昼食後は松尾山(315.4m)へ。

昨年来た時工事していた電波塔は完成していた。

今日は白石畑に下る。

ほどなく白石畑に到着。

ここから後は史跡めぐり。まずは素佐男神社。

しばらく車道を下って平等寺春日神社。

南に向かってまたまた春日神社。

このすぐそばに宮山塚古墳。5世紀後半のものらしい。

ここの少し南に椿井井戸(つばいいど)。

聖徳太子の云われがあって、今も水が湧いている。とても飲めるようなシロモノには見えなかったけれど。
最後に線刻石仏。鎌倉時代のものとか。

竜田川を渡って竜田駅に向かう。

2時半過ぎに竜田駅に到着して、ここで解散となった。
私はこのあとみなさんと分かれてすぐ近くの烏土塚古墳(うどづかこふん)に向かう。

駅から数分の所にある石段を上がって、前方部に上がる。

墳頂からの眺めは素晴らしい。これは明日香方面。

後円部を下りると石室を覗くことができる。

かなり大きくて石舞台古墳に匹敵するくらいの大きさで、その当時(6世紀後半)の平群氏の勢力の大きさを伺わせる。
好天に恵まれて楽しい一日でした。
弥十郎ヶ嶽
土曜日(6/3)は随行で北摂の弥十郎ヶ嶽へ行ってきた。山名は知っていたけれど、行くのは初めてだった。
講師の先生が「同じ講座では同じ山には行かない」というポリシーで数年続けてこられたせいで、もはや遠くて不便な場所しか残っていない。一昔前はマイクロバスをチャーターすることが多かったけれど、バス料金の高騰と受講生の減少というダブルパンチで、どうしても公共交通機関を使わざるを得なくなっている。
しかしさすがにこのポリシーもそろそろ限界という感じで、行ったことのある山を時期やコースを変えて再訪ということにもなりそうだ。
今回も京阪、JR、阪急、能勢電鉄、さらに1日に2便しかないバスで、トータル3時間ほどかけて、篠山の南部の後川(しつかわ)という所までやってきた。4時間くらいかけてやってこられた方もいらっしゃると思う。

少し車道を歩いてから林道に入る。

林道をつめて、いよいよ山道へ。

しばらく谷筋を上がる。

が、このあたりから道が不明瞭になってきた。道があるのか無いのかよくわからないような状態なのだが、所々に古いテープが残っている。
本来のルートはもう少し東の尾根に乗るはずなので、講師の先生と二人でヤブ斜面を強引に上がってルート探索へ。
尾根上も古いテープは所々にあるものの、道らしきものは見あたらない。しかしヤブはそれほど濃くないので、みなさんを誘導してここから山頂に向かう。
八上山石標を発見。

ちょうど昼前に無事、弥十郎ヶ嶽の山頂(715.1m)に到着した。

篠山盆地が眺められるが、木が茂っていて全容は見えない。右の方は多紀アルプス?

下山は篭坊温泉方向へ向かう。
少し下ってハハカベ山石標。

峠を越えて、丈山を目指す。

丈山乗越。

無事、丈山(南峰?)に到着。標高がはっきりしないけれど、多分 723m くらい。弥十郎ヶ嶽より少し高い。

丈山乗越に戻って、農文塾コースを下山する。
フタリシズカ。

ほどなく茶畑に出た。

このあとは車道を 3km ほど歩いて、スタート地点と同じ後川のバス停にゴールした。1日2便のバスの 20 分前くらいに到着した。
こんな機会でも無ければ来られない貴重な山でした。
リトル比良
昨日(5/21)は随行でリトル比良へ行ってきた。とにかく暑い日だった。
リトル比良は何度か歩いているけれど、直近でももう 10 年以上前。はっきりした記憶は無い。
出発時に思いがけないハプニングが発生!!。参加者のチェックを済ませたはずなのに、いざ出ようとすると一人足らない。
この日、初めて参加された方がおられて、同じ方向に向かう別のグループに付いて行かれてしまったようで、幸い連絡がついたので途中で待っていただいて、無事合流できた。
目指す岳山(だけやま)を望む。
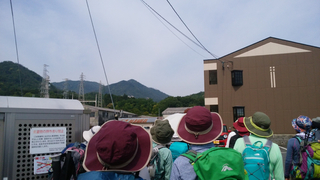
登山口の長谷寺。すでに気温が高い。

少し登って、賽の河原。まったく記憶に無い。

白坂に寄り道。

「弁慶の切石」。この後もこのコースは随所に巨岩があった。

岳観音堂跡。瓦がたくさん落ちていたけれど、わりと新しい感じがした。

暑さのせいか、熱中症ぎみの方が出てきた。休憩を取りながらゆっくり登る。
岳山山頂そばの石造観音三尊。

そして岳山山頂(565m)。

もっと開けて展望のある場所だったような印象があるのだけれど、まったく違っていた。
少し下ったコルのような場所で昼食にした。
昼食後はオウム岩で展望を楽しむ。一番高い山は武奈ガ岳。

これは琵琶湖方面。まだ黄砂の影響が残っているのか、遠方はすっきりしない。

ヒメシャガ。随分めずらしいらしい。

主稜線から分かれて見張山方面へ向かう。
鳥越峰(702m)は何の標識も無かった。

この稜線は歩く人が少ないようで、倒木がたくさんあって道がわかりにくい。数年前までは明瞭なしっかりした道だったそうだけれど。
「鉄砲岩」。

「ろくは石」。

見張山(517.3m)は三角点がある。

少し道をそれて長法寺跡に寄り道。随分大きな寺だったらしい。平安時代から室町時代に栄えたとか。

展望場所からは2月に訪れた沖島。

「馬の足」。

ちょうど下りた所にタニウツギ。

4時前に日吉神社に下山した。

近年は5月にこういう夏日になることがしばしばあるように感じる。
山で暑さにやられるようなことはほとんど無いけれど、基本的に暑い季節は苦手なので、いやな季節がやってきたという感じ。
涼しい所へ脱出したい。
三国岳
先週の金曜日(5/12)は随行で朽木の三国岳へ行ってきた。
桑原橋から登って古屋へ下りるというコースで、部分的には昨秋に歩いている。
以前ならマイクロバスをチャーターして来るような不便な場所なのだけれど、昨今のバス料金高騰と、受講生の減少というダブルパンチのために、堅田からタクシーで桑原橋に乗りつけた。

しばらく植林の急登を這い上がる。
標高が上がるとイワカガミが登場。

休憩を入れながら、スタートして1時間半ほどで丹波越の峠に到着した。

足元にはミヤマカタバミ。

これはオオカメノキというらしい。

峠から1時間ほどで三国岳への分岐に到着。

三国岳の山頂(959m)で昼食となった。ずいぶん山深い不便な場所なのだけれど、個人的にはここ1年ほどで3回目。

下山はまず岩谷峠へ。

ここで実にめずらしいも瞬間に出会えた。



何と、エゾハルゼミが蛹からふ化する瞬間に立ち会えたのだ。
最初に見た瞬間は、ふ化に失敗して死んでいるのかと思ったのだけれど、少ししたら足が動き出した。
羽が次第にしっかりと広がってきて、幹を上に登りだした。さすがに飛ぶまでは至らなかったけれど。
ここからしばらくはシャクナゲがたくさん咲いていた。

沢筋に下り立ったらニリンソウ。

対岸には雪が残っていた。

ちょうど予定の3時に古屋に到着した。

3時に迎えをお願いしていたタクシーがすぐにやってきて、堅田までスムーズに帰ることができた。
京都一周トレイル奥比叡
水曜日(5/10)は京都一周トレイル講座で奥比叡を歩いてきた。
コースは前回終了したケーブル比叡駅をスタートして横川のバス停まで。
随行区間の歩きだけではもの足らないので、朝は八瀬から歩いてケーブル比叡駅まで行って、帰りは横川からせりあい地蔵経由でバス停の登山口まで下った。
9時半にケーブル比叡駅に到着できるように、8時 20 分頃に八瀬を出発した。

天気予報では降水確率が高めだけれど、今のところは雨は降っていない。
先日より頑張ったつもりだったけれど、先日よりも少し時間がかかって峠に到着した。

ガスで幻想的な雰囲気。

ゲレンデ下には前回とほぼ同じく1時間で到着した。

予定通り9時半にケーブル比叡駅に到着して、10 時に歩き始める。小雨がぱらついている。

道の北側にはツツジが植えられている。

随行で来るメリットは、一人ならまず立ち寄らないような場所でゆっくりできるところ。初めて浄土院に入った。

山道脇にクリンソウ。

マムシグサ。

ちょっと寄り道してみろく石仏。

鎌倉初期のもので、破損は信長の焼き討ちのせいとか。
トイレに寄った峰道レストランで昼食にした。

昼食後はせりあい地蔵に向かう。
玉体杉。

回峰行者はここのそばの石に座って御所に向かって祈るのだとか。しかしこの大きな石(写真に撮ってこなかった)、一体どうやってここまで運んだのだろうか。いつごろ設置されたのだろか。表面はずいぶんきれいで、以外と近年の設置かもと感じた。
今週末(5/13)は比叡山のトレイルレースが予定されていて、大会間近ということで随所にテープマークが付けられているが、なぜかコースではないはずのこのあたりにもテープマークがある。
一周トレイルコースはせりあい地蔵から横高山へ登るのだけれど、今回はここで打ち切りで、横川のバス停に向かった。
横川のバス停には午後2時 15 分くらいに到着して、皆さんはここからバスで下山。
時間があるので私はせりあい地蔵まで戻って、ここから登山口のバス停まで下ることにした。
せりあい地蔵から下はトレイルレースのコースで、先日の試走の時に登った道。なかなか苦しかった。
普段はあまり人の歩かない道なのだけれど、下からトレランスタイルの人が上がってきた。こんな直前の平日でも試走に来るひとがいるのかと思ったのだが、近づいてみたら何と鏑木毅さん!! マーキング用のテープを持って登って来られた。
私が下りだったので道を避けたのだけれど、「どうぞどうぞ」ということで通してもらうことにした。
近づいたら「昨年、UTMF でお世話になりました」と一言ご挨拶。そして先ほどのマーキングの件を尋ねてみたところ、今回新設された 50 マイルは後半のループを2回廻るのだけれど、2回目はここの登りは無しで、トレイルコースをそのまま進むとのこと。
鏑木さんの競技に対するストイックな姿勢はつとに有名なのだけれど、おそらくコースのチェックが目的だろうと思われるこの時も、汗びっしょりで登って来られた。半分は自分のトレーニングのつもりなのだろう。
ゆっくりお話しできる状況ではなかったので「どうしてこんなコース設定なのですか?」というような質問はできなかったけれど、よく考えてみると一般ハイカーや観光客との接触を極力少なくするためにああいうアップダウンを設定されたのかなという気もする。
ちょうど今(5/13 14:45)はトレイルレース開催中で、上位選手はすでにゴールしていると思われるが、まだまだ多くの選手はコース上で苦しんでいる時間帯だ。しかも今日は朝はかなりの降雨だったので、コースのコンディションは極めて悪いと思う。
今朝の雨音を聞きながら、トレイルレースへの参加は当分無いだろうと思った。
試走の時は苦しかった登りも下りはすんなりで、横川を出て 45 分くらいでバス停に下り立った。

次回の集合は横川のバス停なので、朝はこのコースを辿るつもりだ。
ポンポン山
月曜日(5/8)は随行で高槻・京都県境のポンポン山へ行ってきた。
ポンポン山はこれまで何度も登っていて、特にマラソンに集中していた頃は家から山麓の神峯山寺まで自転車で行って、ポンポン山2往復なんてこともやっていた。
今日は京都側の善峯寺から周回するコースだったけれど、東海自然歩道は何度か歩いたことがある。
JR の向日市駅からバスで善峯寺へ。善峯寺は花の講座で昨秋に訪れた。
少し車道を上がって、善峯寺の駐車場に入るカーブの所で山道に入る。

善峯寺を望む展望台。以前は木がもっと少なくていい眺めだったらしい。

このあと道が少し不明瞭になって、ヤブの急斜面を這い上がる。

いくつかある登山講座の中では一番の初級クラスなので、ちょっと厳しかったかも。
ほどなく正しい道に合流して、稜線に上がって釈迦岳の東にある展望台で一休み。

天気はいいのだけれど、黄砂のせいで展望はあまりよろしくない。

釈迦岳山頂(630.8m)で昼食。

昼食後、30 分ほどでポンポン山の山頂(678.8m)に到着した。

枚方方面もかすんであまり見えない。

少し戻って、杉谷の方向に下る。

30 分足らずで杉谷へ。

あとは車道で善峯寺に戻る。

シャガ?

25 分ほどの車道歩きで善峯寺のバス停に戻って、無事解散となった。
のんびりした一日でした。
地蔵山、愛宕山
日曜日(4/16)は随行で地蔵山と愛宕山へ行ってきた。
4月から新しい期になって、今期は定員一杯の 25 名という大所帯。しかも前日の時点では全員ご参加とのことで、面識の無い方も何名かおられて、行方不明者が出たりしないかという不安を感じながらのスタートだった。
ところが朝に JR で霧のためのダイヤの乱れがあって、滋賀県から来られる数名の方がバスの時刻に間に合わないことになってしまった。
1名は初めての方で、致し方なく欠席されることになってしまったが、6名の方々は京都駅で出会われたようで、別ルートで愛宕山を目指して、できれば午後に合流ということになった。
当日の都合で欠席された方もあって、結局スタート時点では 16 名だった。
八木駅からバスで越畑へ行って、ここから芦見峠へ向かう。

棚田のあるのどかな道を進んで、登山道に入る。

30 分少々で芦見峠に到着。

植林の樹林帯を1時間少々登って、地蔵山(947.3m)に到着。ここは愛宕山よりも高い。

少し下ると前方に愛宕山。

愛宕スキー場の跡で昼食にした。ここにはスキー場を開発した中山再次郎氏の像があったが、戦争で金属を供出さされて、残っているのは台座のみ。伊吹山には像が残っている。

昼食後は愛宕山の三角点(889.8m)へ寄り道した。一人だったら寄らない所。

遠くに比良山系が望めた。

このあと、愛宕神社で別ルートの6名の方と無事合流できた。

総勢 22 名で大杉谷を下る。

午後3時過ぎに清滝のバス停で解散となった。

その後は数名の方々と一緒に、清滝川から保津峡駅まで歩いた。保津峡駅のあたりはいつもこの時期は山桜がきれいだ。

